ニュージーランドは、その冷涼な気候と多様なテロワールで世界的に評価される「ニューワールド」の代表的なワイン生産地です。特にソーヴィニヨン・ブランやピノ・ノワールは世界中のワイン愛好家を魅了しています。手つかずの自然が広がるこの国は、その革新的なワイン造りの精神とともに、常に新しい挑戦者たちを受け入れてきました。近年、この豊かな大地で独自の哲学と情熱を胸にワイン造りに挑む日本人醸造家たちが注目を集めています。彼らは日本の繊細な感性とニュージーランドの豊かな自然を融合させ、唯一無二のワインを生み出しています。彼らの存在は、ニュージーランドワインの多様性と国際的な魅力を一層高めるものとして、世界中のワイン愛好家から熱い視線が注がれています。彼らの挑戦は、単に高品質なワインを造るだけでなく、ニュージーランドワインの新たな可能性を切り開く、まさに「日本の足跡」を刻むものと言えるでしょう。
目次
ニュージーランドの「自由」が日本人醸造家を惹きつける理由
ニュージーランドのワイン産業は、「自由な精神」と「規制の少なさ」が大きな特徴です。フランスのAOC(原産地統制呼称)やイタリアのDOCG(統制保証原産地呼称)のような旧世界の厳格な制度とは異なり、ニュージーランドではブドウ品種の選択や醸造手法において、生産者の裁量が非常に大きく、多様な試みが可能です。この柔軟な環境は、ワインメーカーが自身の個性や理想を追求しやすい大きな利点となっています。例えば、特定のブドウ品種に縛られることなく、その土地のテロワールに最も適した品種を選び、あるいは新しい品種の可能性を探るといった自由な発想が許されています。また、醸造過程においても、伝統的な手法に固執せず、最新の技術や独自のアイデアを積極的に取り入れることができるため、革新的なワインが次々と生まれています。
多くの日本人醸造家は、ソムリエ、金融、不動産、農業といった多様なバックグラウンドを持っています。彼らはそれぞれ独自の哲学、例えばオーガニック農法、バイオダイナミック農法、ドライ・ファーミング、最小限の介入、特定の香りプロファイルへのこだわり、あるいは亜硫酸無添加といった考えをワイン造りに持ち込んでいます。このような異業種からの転身者にとって、ニュージーランドの柔軟な環境は、自身の経験や哲学をワイン造りに反映させる上で計り知れない魅力があるのです。旧世界では、長年の伝統や厳格なルールが新規参入者にとって障壁となることも少なくありませんが、ニュージーランドでは「失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる土壌」が根付いています。この開かれた精神があるからこそ、ニュージーランドはわずか数十年で世界クラスのワイン生産地へと成長できたとも言えるでしょう。この自由な環境が、日本人醸造家が自身のビジョンを具現化するための理想的なキャンバスとなっているのです。彼らの多様な視点と挑戦意欲が、ニュージーランドワインのさらなる進化を促しています。
個性豊かな日本人醸造家たちの物語
ニュージーランドのワインシーンで活躍する日本人醸造家たちは、それぞれが独自の物語と哲学を持ち、その土地のテロワールと日本の感性を融合させたワインを造り出しています。彼らの挑戦は、ニュージーランドワインの多様性をさらに深めています。
木村滋久氏とキムラ・セラーズ (マールボロ)
木村滋久氏は1973年東京生まれで、ザ・キャピトルホテル東急でソムリエとして活躍されていました。ワインの「飲み手」としての経験を通じて、「造り手」への転身を決意されたそうです。フランスでのワイナリーツアーでブドウ畑の情景、醸造所の香り、そして生産者の情熱に深く魅了されたことが、彼がワイン造りの道に進む決定的なきっかけとなりました。2004年にニュージーランドへ渡り、リンカーン大学でブドウ栽培とワイン醸造学を学び、その後、複数のワイナリーでの研鑽を経て、2009年に妻の美恵子さんと共に「キムラ・セラーズ」を設立されました。
木村滋久氏のソムリエとしての経験は、彼のワイン造りの哲学に深く影響を与えています。彼は「飲み手」の視点から「熟成を待たずにすぐに楽しめる、美味しいワイン」を追求されており、これはソムリエとして顧客の反応を直接見てきた経験が反映されたものと考えられます。ワインを通じて「多くの笑顔が溢れる瞬間」を提供したいという彼の願いは、単なる技術的な品質追求に留まらない、ワインがもたらす「体験」を重視するサービス業出身者ならではの哲学を示しています。キムラ・セラーズのワイン造りの哲学は、「ニュージーランドらしいソーヴィニヨン・ブラン」を追求することにあり、木村氏は「パッションフルーツやグレープフルーツなど、ニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランには本当にたくさんのアロマがあり、それが重なり合ってできています。その何重ものアロマを表現したい」と力強く語られています。2018年には0.7ヘクタールの自社畑を購入し、除草剤や殺虫剤を使用しないオーガニック農法を実践されています。収穫時などの繁忙期以外は夫婦二人で運営する小規模生産体制を貫いており、その丁寧な手仕事がワインの品質に反映されています。彼らのワインは国内外で高く評価されており、特にソーヴィニヨン・ブランはNIKKEIプラス1の「食卓を彩るワイン(3000円以内)」で2位にランクインした実績もあります。
小山竜宇氏とコヤマ・ワインズ (ワイパラ・ヴァレー)
神奈川県出身の小山竜宇氏は、「物づくりをする仕事がしたい、ワインを造りたい」という強い思いから、2003年にニュージーランドへ渡られました。国立リンカーン大学でブドウ栽培とワイン醸造の修士課程を修了され、冷涼気候のカリキュラムが充実していたことがこの大学を選んだ理由の一つだそうです。在学中の2004年から、ピノ・ノワールで名高いプレミアムワイナリー「マウントフォード」でアシスタント・ワインメーカーとして働き、イタリアのトスカーナやドイツなど海外での醸造研修も積極的に行い、技術を磨かれました。
小山氏は、理想のワイン造りを追求するため、2009年に自身のブランド「コヤマ・ワインズ」を設立されました。ワイナリーはニュージーランドで最も新しく、急成長を遂げる冷涼気候の産地ワイパラに拠点を置いています。ワイパラは乾燥し、南風が吹き、穏やかな日照が長く続く地域で、特にピノ・ノワール栽培に適した石灰岩粘土質土壌が広がっています。小山氏は、ニュージーランド全体の2%しかないとされるこの石灰質土壌から、他の産地では見られない繊細さや美しさを表現されています。彼のワイン造りの信念は、「土地と自らのスタイルを純粋に表現すること」であり、理想的なテロワールから上品でエレガントなピノ・ノワールと旨み溢れるリースリングを手掛けています。コヤマ・ワインズのラベルには、小山氏の名前「竜宇」にちなんだ竜が描かれています。小山氏のワイン造りは、ニュージーランドの「冷涼気候」と「石灰質土壌」という特定のテロワール要素への深い理解と探求に基づいています。これは、特定の気候・土壌条件がワインの個性形成に決定的な影響を与えるという、テロワール主義の明確な実践例です。
佐藤嘉晃・恭子夫妻とサトウ・ワインズ (セントラル・オタゴ)
佐藤嘉晃氏と妻の恭子氏は、東京とロンドンで国際金融のプロフェッショナルとしてキャリアを積んだ後、ワインへの情熱を追求するためニュージーランドへ移住されました。クライストチャーチのリンカーン大学でブドウ栽培とワイン醸造のグラデュエート・ディプロマを修了した後、世界最南端のワイン産地であり、ピノ・ノワールの銘醸地として知られるセントラル・オタゴにたどり着かれました。嘉晃氏は、フェルトン・ロードやマウント・エドワードといったセントラル・オタゴの名門ワイナリーで2年間研鑽を積んでいます。
佐藤夫妻のように国際金融業界からワイン造りへと転身する日本人醸造家が複数見られることは、ニュージーランドのワイン産業が、単なるビジネス機会だけでなく、個人の深い情熱やライフスタイル、自己実現を追求する場として魅力を持っていることを示唆しています。安定したキャリアを捨ててまでワイン造りに挑む彼らの選択は、品質への妥協なきこだわりと、自然と共生する持続可能なワイン造りへの強い信念に裏打ちされており、結果として「カルトワイン」と評されるような個性的なワインを生み出す原動力となっています。
2009年に「サトウ・ワインズ」を設立し、最初のヴィンテージとして有機ブドウから250ケースのピノ・ノワールを生産されました。以来、彼らは有機栽培のブドウを調達し続け、現在は約1700ケースを生産されています。2016年初頭には、クロムウェル近郊のマウント・ピサに5ヘクタール(実質3.2ヘクタール)の自社畑「ラ・フェルム・ド・サトウ」を購入し、化学物質不使用の東向き斜面にカベルネ・フラン、シャルドネ、シュナン・ブラン、ガメイ・ノワール、ピノ・ノワールを植樹されています。彼らの哲学は、オーガニックおよびバイオダイナミック農法に深く根ざし、醸造過程での介入を最小限に抑えることです。商業酵母を使わず自然発酵を促し、発酵中の添加物を避け、瓶詰め直前にごく少量の亜硫酸を使用するのみです。彼らは「ワインは農業」であり、「年によってブドウもワインも変わる」という自然との共生を重視されています。セントラル・オタゴの美しい風景を飲み手に届けられるようなワインを造りたいと語られています。自社畑「ラ・フェルム・ド・サトウ」からのワインは2022年に初リリースされ、すでにカルト的な人気を博し、「素晴らしい醸造家による見事なカルトワイン」と評されています。
楠田浩之氏とクスダ・ワインズ (マーティンボロ)
楠田浩之氏は1964年埼玉県生まれで、大学卒業後、富士通などの大企業メーカー、そしてシドニーの総領事館に勤務するという異色の経歴を持っています。しかし、「大企業や国という大きな看板を背負うよりも個人の力で自分がどこまで通じるのかを試そう」という思いからワイン造りの道を決意されました。ドイツのガイゼンハイム大学でブドウ栽培・ワイン醸造学部を修了し、フランスのブルゴーニュでの研修も経験されました。2001年5月に家族と共にニュージーランドへ移住し、同年10月にピノ・ノワールの銘醸地マーティンボロに「クスダ・ワインズ」を設立されました。彼は特に冷涼な南半球のピノ・ノワールに魅力を感じていたそうです。
楠田氏のワイン造りの目標は、「純粋さと繊細さを備えたピノ・ノワールを造ること」です。彼は、世界最高レベルで認められるピノ・ノワールを生産するという夢を追い求めています。夜は自宅に戻った後も世界各国の銘柄を取り寄せて分析するなど、ワイン研究に余念がありません。彼の徹底した自己理念の達成への地道な努力は、ニュージーランド国内外の生産者やマスター・オブ・ワインから高い評価と賛辞を受けています。楠田氏の「徹底した自己理念の達成」と「飽くなき研究」は、多くの日本人醸造家が持つ「職人気質」を強く示しています。これは、細部へのこだわり、品質への妥協なき追求、そして自身の哲学をワインに深く反映させる姿勢を指します。その結果、彼らのワインは単なる技術の産物ではなく、繊細で多層的な味わい、そして造り手の魂が宿る「作品」としての価値を高めています。この職人気質は、ニュージーランドワインの多様性と深みを一層豊かにしていると言えるでしょう。
大沢泰造氏と大沢ワインズ (ホークス・ベイ)
滋賀県の米原で不動産事業や農業事業を手がける大沢泰造氏にとって、「大沢ワインズ」は長年の夢の結晶です。様々な農業国を視察した結果、ニュージーランド北島のホークス・ベイが自身の目指す農業に最適と判断されました。元々は羊の放牧地だった約43ヘクタールの土地を購入し、2006年にゼロからブドウ畑を開墾されました。これにより、日本人オーナーが所有するニュージーランドでは珍しい「単一畑ワイナリー」となっています。
大沢泰造氏の不動産・農業事業という異業種からの参入は、他の日本人醸造家とは異なる「規模とビジョン」をニュージーランドワイン産業にもたらしています。彼が広大な土地をゼロから開墾し、大規模な単一畑ワイナリーを設立した背景には、ビジネスとしての戦略的思考と長期的な視点があります。これは、単なる情熱だけでなく、日本の資本と経営手腕がニュージーランドのワイン生産に新たな可能性を切り開いていることを示しています。
大沢ワインズは、「最高のワインは最高のブドウから生まれる」という信念のもと、ブドウ栽培の品質を最優先しています。現代的で環境に配慮した醸造施設を備え、情熱と新しい技術を持つ専門家たちと協力してワイン造りを行っています。ブドウの枝、葉、果実に関する全ての作業は、経験豊富な職人によって手作業で行われ、土地の特性を最大限に表現し、ニュージーランド独自の風味を追求しています。醸造家ロッド・マクドナルド氏との協業により、自然と調和したブドウ栽培を実践されています。大沢ワインズは受賞歴も豊富で、「日本で飲もう最高のワイン2016 赤/フルボディ部門 専門家Gold賞」をはじめ、国内外のコンテストで多数の賞を獲得しています。
岡田岳樹氏とフォリウム・ヴィンヤード (マールボロ)
東京都出身の岡田岳樹氏は、北海道の農学部を卒業後、醸造学の権威であるカリフォルニア大学デービス校でワイン造りを学びました。2003年にワーキングホリデービザでニュージーランドに渡り、フランスの老舗アンリ・ブルジョワがニュージーランドで手掛ける「クロ・アンリ」で栽培責任者として研鑽を積みました。2010年6月、マールボロのブランコット・ヴァレーに「フォリウム・ヴィンヤード」を設立しました。
岡田氏は、マールボロで他との差別化を図るため、水やりを行わない「ドライ・ファーミング」を実践しています。これは、ブドウの生育に大きな影響を与える水をあえてコントロールせず、その年々の雨量に任せることで、「ヴィンテージごとの特徴」を最大限に引き出すという哲学に基づいています。彼は「そもそも欧州では水やりが禁止されているので、世界的に見れば特別なことではない」と述べていますが、マールボロでは珍しい手法です。ブランコット・ヴァレーの粘土質土壌は保水性が良く、ドライ・ファーミングに適しています。岡田岳樹氏のドライ・ファーミングの実践は、旧世界の伝統的なワイン造りの知見をニューワールドであるニュージーランドに応用した革新的な試みです。これにより、ヴィンテージごとの個性が際立つ、よりテロワールを反映したワインが生まれています。このアプローチは、日本人醸造家が旧世界の伝統的な知見とニューワールドの柔軟性を融合させ、ワインの多様性と品質を向上させていることを示唆しています。
フォリウム・ヴィンヤードは、「高品質なワインは高品質なブドウから」という信念のもと、高密植栽培により凝縮した果実味を持つブドウを育てています。2014年には有機農業認定機関「BioGro」の認定を取得し、オーガニック農法を実践しています。岡田氏のソーヴィニヨン・ブランは、マールボロ特有の華やかさに加え、鉱物系のミネラル感やほのかな塩味、複雑さを持ち合わせていると評されています。ピノ・ノワールは「出汁のようにしみじみする味わい」と表現されるほどの滋味深さがあります。ワイン・アドヴォケイトでは、2014年から2016年ヴィンテージの計6銘柄中4銘柄が90点を超える高得点を獲得し、その品質の高さが証明されています。
品質へのこだわりとテロワール表現の追求
ニュージーランドで活躍する日本人醸造家たちは、出身や背景は様々ですが、共通して「最高のブドウから最高のワインを」という品質への強いこだわりを持っています。彼らは、マールボロの多層的なアロマを持つソーヴィニヨン・ブラン、ワイパラの石灰質土壌が育む繊細なピノ・ノワール、セントラル・オタゴの冷涼な気候が凝縮する果実味など、各地域のテロワールを最大限に表現することに情熱を注いでいます。彼らのワイン造りにおける「品質へのこだわり」は、単なる技術的な追求に留まらず、ニュージーランドの多様な「テロワール」を深く理解し、それを最大限に表現することに集約されています。
彼らは環境への配慮と持続可能性を重視し、オーガニック農法(キムラ・セラーズ、フォリウム・ヴィンヤード)、バイオダイナミック農法(サトウ・ワインズ、グリーンソングス)を積極的に取り入れています。これらの農法は、土壌の健康を保ち、ブドウ本来の生命力を引き出すことを目的としています。例えば、バイオダイナミック農法では、月の満ち欠けや天体の動きを考慮した作業を行い、特定のハーブや天然素材を用いた調合剤を畑に散布することで、生態系のバランスを整え、健全なブドウを育んでいます。また、フォリウム・ヴィンヤードの岡田岳樹氏のように、マールボロでは珍しいドライ・ファーミングを実践し、ヴィンテージごとの個性を追求する革新的なアプローチも見られます。これは、灌漑をせず、ブドウが自然の雨水だけで育つようにすることで、その年の気候変動がワインの味わいに直接反映され、よりテロワールを忠実に表現するワインが生まれるという哲学に基づいています。久能ワインズの中野雄揮氏は亜硫酸無添加の自然派ワイン造りにこだわり、「日本職人の味」を表現しています。これらの多様な実践は、ニュージーランドワインの表現の幅を広げ、世界市場における競争力を高めています。多くの日本人醸造家が、オーガニック、バイオダイナミック、ドライ・ファーミング、亜硫酸無添加といった「持続可能性」と「自然派」のアプローチを共通して重視している点は、単なるトレンド追随ではなく、彼らの深い環境意識と、ブドウ本来の力を最大限に引き出すという哲学の表れです。
日本文化とワイン造りの融合
日本人醸造家たちは、そのワイン造りやブランディングに自身のルーツである日本文化の要素を巧みに融合させています。例えば、キムラ・セラーズのラベルには、ニュージーランドのシダ(コル)と日本の桜がデザインされ、両国の架け橋となる願いが込められています。このデザインは、二つの国の自然と文化が融合し、新しい価値を生み出すという彼らのワイン造りの精神を象徴しています。久能ワインズは、中野氏の母方の祖父母の珍しい苗字をブランド名に冠し、将来消滅する可能性があったその苗字をワインのレーベルとして形に残したいという思いが込められています。また、そのワインの味わいを「懐石料理のように層が細かく幾重にもある」と表現するなど、日本の食文化に通じる繊細さや複雑さを追求しています。
さらに、グリーンソングスのワインが和食店や鮨店でも人気があるように、和食とのペアリングを意識したワイン造りを行う醸造家もおり、ニュージーランドワインの新たな楽しみ方を提案しています。彼らは、和食の繊細な風味を邪魔せず、むしろ引き立てるような、バランスの取れた酸味や旨味を持つワインを追求しています。この文化的な融合は、彼らのワインに独自のアイデンティティを与え、特に日本市場において強い共感を呼ぶとともに、国際的にもニュージーランドワインの多様な魅力を発信する役割を担っています。これは、ワインが単なる飲料ではなく、文化や物語を伝える媒体としての可能性を広げていることを示唆しています。彼らのワインは、日本の「おもてなし」の心や「職人気質」が宿る、まさに「飲む芸術品」と言えるでしょう。
ニュージーランドワインの未来を拓く日本人醸造家たち
ニュージーランドで活躍する日本人ワイン醸造家たちは、その多様なバックグラウンドと揺るぎない情熱、そして革新的なアプローチによって、ニュージーランドワインの品質向上と多様化に大きく貢献しています。彼らは、冷涼気候のテロワールの可能性を最大限に引き出し、オーガニックやバイオダイナミック農法、ドライ・ファーミング、亜硫酸無添加といった持続可能で自然なワイン造りを牽引しています。また、日本の繊細な感性や職人気質をワインに吹き込むことで、国際市場におけるニュージーランドワインの独自性と魅力を高めています。
彼らの成功は、ニュージーランドが「ニューワールド」でありながらも、伝統的なワイン産地にも劣らない深みと個性を追求できる地であることを証明しています。ソムリエ経験を活かした「飲み手目線」のワイン造り、特定のテロワールへの専門的探求、金融業界からの転身に見る情熱の追求、職人気質による品質の飽くなき追求、異業種からの参入による規模とビジョンの拡大、旧世界の伝統技術の革新的な応用、日本の酒造メーカーとの連携、そして多国籍な経験がもたらす多様な表現と和の感性の融合。これら多角的なアプローチは、日本人醸造家がニュージーランドワインの未来を拓く上で不可欠な存在であることを示しています。彼らは、ニュージーランドワインの品質と多様性を高めるだけでなく、そのブランドイメージに深みと物語性を与え、世界中のワイン愛好家にとってより魅力的なものにしています。今後も、彼らの挑戦はニュージーランドワインの新たな地平を切り開き、世界中のワイン愛好家を魅了し続けることでしょう。

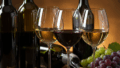

コメント