目次
ブルゴーニュワインとは 土地の個性を追求する哲学
フランス北東部に位置するブルゴーニュ地方は、世界で最も評価の高いワインの一つを生産する地として知られています。ボルドーと並び称されるフランスの二大ワイン産地であり、特にピノ・ノワールとシャルドネといった単一品種でのワイン造りが大きな特徴となっています。この地方のワインは、「テロワール」と呼ばれる土地の個性を極めて重視しており、畑ごとの微細な土壌、地形、気候の違いがワインの味わいに明確に反映されることで、その複雑性と多様性が生み出されています。
ブルゴーニュは「生きる伝説」と称され、ロマネ・コンティやモンラッシェといった世界最高峰かつ最高額のワインを数多く輩出しています。特にグラン・クリュ(特級畑)は生産量が全体のわずか1.4%と極めて希少であり、その品質と価格は世界中のワイン愛好家を魅了し続けています。この希少性が、ブルゴーニュワインの価値を一層高めています。一本のロマネ・コンティが数百万、時には数千万円の値をつけることも珍しくなく、それは単なる品質の高さだけでなく、その土地の歴史、生産者の哲学、そして極めて限られた生産量という複合的な要因によって支えられています。
ブルゴーニュを深く理解するためには、「アペラシオン」の知識が鍵となります。北から南まで多様なアペラシオンを把握することが、ブルゴーニュワインを理解する上で根幹をなすと言われています。地理的には、ブルゴーニュ地方の中心都市であるディジョンにはブドウ畑がなく、車でわずか15分ほど南下するだけで、すぐに名高いコート・ド・ニュイ地区のブドウ畑が広がる光景を目にすることができます。また、ブルゴーニュ地方の最南端に位置するボージョレ地区は、行政上はローヌ県に属するため、ブルゴーニュの住民にとっては「ブルゴーニュではない」と認識されることもあるようです。これは、ワインのスタイルや主要品種が他のブルゴーニュ地域と異なるため、文化的な境界線が存在することを示唆しています。ブルゴーニュワインは、まさにその土地の「アイデンティティ」をボトルに閉じ込めた芸術品と言えるでしょう。
歴史が育んだブルゴーニュワインの礎
ブルゴーニュにおけるワイン造りの歴史は非常に長く、その起源は古代ローマ時代にまで遡ります。約2000年前、ガリア地方(現在のフランス)がローマ帝国に征服されたことにより、地中海沿岸からワイン造りの技術がこの地域に伝播しました。南から侵攻したローマ軍がブドウを植え、遊牧民を定住させ、区画ごとに畑を任せたことがワイン造りの始まりとされています。4世紀頃には、ブルゴーニュは既にワイン銘醸地としての地位を確立していたと言われています。ローマ人たちは、ブルゴーニュの冷涼で湿度の高い気候が、後にこの地の主要品種となるシャルドネやピノ・ノワールといったブドウに適していることを発見し、ワイン生産を本格化させていきました。ブドウの栽培方法、収穫時期の決定、果実の選別、圧搾、そして木樽での保存といった基本的なワイン造りの技術は、古代ローマ時代から現代に至るまで受け継がれています。
中世に入ると、ワイン造りはキリスト教の修道院、特にシトー派やクリュニー派の修道院によって大きく発展しました。彼らは、自給自足のためだけでなく、教会の儀式用や外部への販売による収益化を目的として、高品質なワインを追求しました。修道院の僧侶たちは、それぞれの畑の土壌や日当たり、水はけなどの微細な違いがワインの味わいに影響を与えることに気づき、これを「テロワール」として捉える考え方を確立しました。「修道院の人が土地による味わいの違いに気付く」という言葉が、その貢献の大きさを物語っています。彼らは、同じ品種のブドウであっても、異なる区画で栽培されたものが異なる風味を持つことを発見し、その違いを記録し、最適な栽培方法を模索しました。シトー派にとってチーズも神聖な文化であり、ワイン造りとともにチーズも作られた歴史もあります。特に質の高い土地は石垣や塀で囲まれ、「クロ(Clos)」と呼ばれ、その名は現在も多くの畑に残っています。これは、修道院が畑の境界を明確にし、品質を維持しようとした証です。
14世紀にはブルゴーニュ公国が築かれ、その歴代公爵はワインの名声を高める上で決定的な役割を果たしました。特に1395年、フィリップ豪胆公は品質の低いガメイ種の栽培を禁止し、この土地に合った高品質なピノ・ノワール(当時は「ノワリアン」と呼ばれた)の栽培を奨励しました。この勅令は、今日のブルゴーニュワインの品質の方向性を決定づけるものとなり、ブルゴーニュワインは上流階級の間で広く飲まれ、ヨーロッパ各国の宮廷や教皇庁にまで流通するようになりました。
フランス革命は、ブルゴーニュのワイン産業に大きな転換点をもたらしました。修道院や貴族が所有していた広大な畑が分割され、ブルジョワジーや市民の手に渡ったことで、「ドメーヌ」と呼ばれる小規模な生産者が多数誕生するきっかけとなりました。これにより、各ドメーヌがそれぞれの区画のテロワールを深く掘り下げてワインを造るという、現在のブルゴーニュの生産体制の根幹が形成されました。ルイ14世の子孫の相続争いをきっかけに、畑がさらに細かく分割され、小区画「リューディ」が広まったとされています。また、元々遊牧民であった人々が織物販売から派生してブドウの取引を始め、「ネゴシアン」が誕生しました。ネゴシアンは、ブドウを買い集めてワインを醸造し、販売する役割を担い、1980年頃まではブルゴーニュワイン産業の主流を占めていました。しかし、近年は自社畑でブドウを栽培し、醸造から瓶詰めまで一貫して行う「ドメーヌ」が、よりテロワールを忠実に表現できるとして注目されるようになっています。長い歴史の中で、ブルゴーニュのワイン造りは多くの変遷を経て、現在の複雑な構造を形成していきました。そして、1947年に制定されたクリマ(気候区画)は、その歴史的・文化的意義が認められ、2015年に世界文化遺産に登録されています。
テロワール ブルゴーニュワインの魂を形成する要素
ブルゴーニュワインの根幹をなす概念が「テロワール」です。「テロワール」とは、ブドウが育てられた土地の個性であり、その土地の土壌、地形、気候などの自然条件が、ブドウひいてはワインの味わいや香りに影響を与えるという包括的な概念を指します。ブルゴーニュでは、このテロワールが極めて重要視されており、畑ごとにそのランク付けが行われているほどです。ブルゴーニュの生産者は、このテロワールを「ワインの魂」と捉え、その個性を最大限に引き出すことに情熱を注いでいます。
テロワールは、主に以下の3つの要素から構成され、それぞれがワインの風味と特性に独自の貢献をしています。
土壌
土壌の特性は、ワインの味わいに直接的な影響を与えます。粒子の大きさ、例えば粘土質か砂利質かによって水はけの良さが変わり、これがブドウの生育とワインのスタイルに影響を与えます。粘土質土壌は水分を保持しやすく、ブドウの生育をゆっくりと促し、より力強く複雑なワインを生み出す傾向があります。一方、砂利質土壌は水はけが良く、ブドウの根が深く伸びることを促し、ミネラル感豊かでエレガントなワインにつながることが多いです。地質もまた重要であり、花崗岩、火山岩、泥灰岩、石灰岩、シストといった変成岩の種類や、混入している堆積した有機物などがワインの味わいを形成します。ブルゴーニュの土壌は基本的に粘土が混ざった石灰質土壌であり、その割合や形成された年代の違いが、ワインの味わいの微細な違いにつながっています。具体的な例として、貝などの化石を多く含む石灰質土壌ではミネラルが豊富な味わいに、石灰層では繊細でキレイな酸、花崗岩層では芳醇な香り、泥灰岩層ではパワフルな果実味を持つワインが生まれることが知られています。
地形
畑の地形は、ブドウの日照量、気温、湿度、風通し、水はけに大きな影響を与え、結果としてワインの風味を左右します。畑の標高、平地か斜面か、そして斜面の方角(南向き、北向きなど)が特に重要です。ブルゴーニュの上級畑はすべて丘の斜面に沿って広がっており、この斜面はブドウの生育にとって理想的な条件を提供します。例えば、効率的な日照確保によるブドウの熟度向上は、糖度とアロマの凝縮を促します。また、冷たい空気の滞留防止による霜害の軽減は、ブドウの生育サイクルを安定させます。表土が少なく根が深く伸びることで、ブドウは土壌の奥深くにある複雑なミネラル成分を吸い上げ、これがワインに深みと複雑性を与える要因となります。さらに、雨水が流れ水分過剰になりにくいことによる風味の凝縮と病害の減少といったメリットがもたらされ、健全で高品質なブドウが育ちます。
気候
気候は、降水量、気温とその変化(寒暖差)、日照量、風速などが含まれます。ブルゴーニュは冷涼から温和な大陸性気候に属しますが、厳密には西岸海洋性気候の影響も受けます。特に昼夜の寒暖差が大きいことがワインに良い影響を与えます。日中の高い気温はブドウの光合成を促進し、糖分の蓄積を促します。一方、夜間の気温低下はブドウの呼吸量を減らし、糖分や酸の消耗を抑えます。この昼夜の寒暖差が大きいほど、ブドウの酸が保たれ、糖度とのバランスがとれた、より複雑な味や香りの成分を生み出すとされています。また、大きな寒暖差は、タンパク質や炭水化物、ビタミンといった微小な成分の生成にも影響を与え、ワインの骨格やアロマの複雑性を高めます。同じ畑であっても、栽培された年(ヴィンテージ)によって気候は異なり、ブドウの出来具合に大きく関わるため、ヴィンテージごとのワインの個性が生まれます。
ピノ・ノワールとシャルドネは、その品種特性として土壌の特性を非常に忠実に反映するブドウです。この特性があるため、ブルゴーニュでは隣接する畑であっても土壌の種類が微妙に異なるだけで、ワインの風味に大きな違いが生まれるのです。これがブルゴーニュワインの多様性と複雑性の根源となっています。ドメーヌ・ルフレーヴの言葉にもあるように、「ブドウ栽培に適した畑は、他の作物の栽培には向かない『不毛』と評されるような厳しい環境であることが多く、それが素晴らしいブドウを生む」という逆説的な事実が、ブルゴーニュワインの品質の根源を物語っています。痩せた土壌や良好な水はけ、急な斜面といった環境は、ブドウ樹が自ら深く根を張り、土壌の奥深くからミネラルを吸い上げることを促します。このブドウ樹の「努力」が、ワインに深みと複雑性をもたらし、その土地の「テロワール」が最大限に表現された、唯一無二の「偉大なワイン」を生み出すのです。
ブルゴーニュを彩る主要ブドウ品種とその魅力
ブルゴーニュワインは、ボルドーワインが複数品種をブレンドするのとは対照的に、ピノ・ノワール、シャルドネ、アリゴテ、ガメイといった品種を単一で醸すことが基本です。この単一品種主義は、長い歴史の中でブルゴーニュの土地に最も適した品種を見極めた結果であり、それぞれの品種が持つ個性を最大限に引き出すことを可能にしています。これにより、ワインはより純粋にその品種とテロワールの特徴を表現します。
ピノ・ノワール (Pinot Noir)
ピノ・ノワールは、世界最高峰の黒ブドウ品種と称され、ブルゴーニュの粘土石灰質の土壌と最高の相性を持つことで知られています。この品種から造られる赤ワインは、タンニンが少なめでありながら酸度が高く、若いうちはラズベリーやチェリーのような赤系果実のフレッシュな香りが特徴的です。熟成させることで、トリュフ、キノコ、なめし革、森の下草、スパイス、紅茶、タバコといった複雑で芸術的なブーケへと変化し、その味わいはより深みを増します。そのスタイルは力強くもエレガントであり、非常に長い熟成に耐えうる品格あるワインを生み出します。ピノ・ノワールは栽培においてかなり土壌を選び、特に粘土石灰質土壌がその品質を最大限に引き出すとされます。この品種は土壌の特性を非常に忠実に反映するため、単一品種・単一畑で造られるブルゴーニュのピノ・ノワールは、ヴィンテージごとの気候の違いが味わいに明確に現れます。ボルドーのように複数のブドウをブレンドしてヴィンテージの差を小さくすることができないため、その年の気候がワインの個性を大きく左右します。主な産地としては、赤ワインの9割を占め、名だたるグラン・クリュが集結するコート・ド・ニュイ地区が挙げられます。ジュヴレ・シャンベルタンやヴォーヌ・ロマネなどがその代表的な村です。
シャルドネ (Chardonnay)
シャルドネは、世界で最も広く栽培されている白ブドウ品種の一つであり、ブルゴーニュの石灰岩質の土壌と相性が良く、世界最高峰の白ワインを生み出しています。熟した果実の充実感と樽由来のリッチなフレーバーを合わせ持ち、そのスタイルは非常に多様です。シャブリのようにフレッシュで軽やかなものから、コート・ド・ボーヌのムルソーやピュリニー・モンラッシェのように、ナッティでボリューミーなリッチなものまで、幅広い表現が可能です。若いうちは柑橘類や白い花の香りが特徴的ですが、熟成とともにヘーゼルナッツ、バター、蜂蜜、トースト、ミネラルといった複雑なアロマが展開します。シャルドネは、ピノ・ノワールほど土壌を選ばないと言われますが、育つ土壌によってその風味は大きく異なります。ピノ・ノワールと同様に土壌の特性をよく反映する品種であるため、隣接する畑であっても土壌の種類が微妙に異なるだけで、ワインの風味に大きな違いが生まれます。白ワインで有名なシャブリ地区やコート・ド・ボーヌ地区が主要な産地です。特にピュリニー・モンラッシェは「世界最高峰の白ワイン」を生み出す銘醸地として知られ、強い石灰質土壌が力強いミネラルに溢れたワインを生み出す特徴を持ちます。
アリゴテ (Aligoté)
アリゴテは、ブルゴーニュの中央に位置するマコン地区やコート・シャロネーズなどで主要に栽培される白ブドウ品種です。酸度が高いことが特徴ですが、熟成させることで素晴らしい白ワインになるポテンシャルを秘めています。若いうちはレモンや青リンゴのような爽やかな酸味が際立ちますが、熟成すると蜂蜜やナッツのニュアンスも現れます。ワインカクテル「キール」を生み出した品種としても有名で、カシスリキュールと合わせて食前酒として楽しまれています。コート・シャロネーズのブーズロン村では、地中海性気候を活かして高品質なアリゴテが栽培されており、柑橘系の香りとシャープな酸、ほどよい果実味のバランスが取れたワインが生まれます。
ガメイ (Gamay)
ガメイは、ブルゴーニュの最南端に位置するボージョレ地区の主要品種です。ボージョレ地区の花崗岩土壌との相性が非常に良く、素晴らしい品質のガメイが生み出されます。一般的にはボージョレ・ヌーヴォーの主要品種として知られ、バナナやイチゴのような新鮮な果実味を楽しむ早飲みタイプのワインが主流です。しかし、クリュ・デュ・ボージョレと呼ばれる特定の高品質な畑では、長期熟成に耐えうる繊細かつ深みのある赤ワインも生産されています。これらのクリュ・ボージョレは、ピノ・ノワールを思わせるような複雑な香りと味わいを持ち、熟成によってさらにその真価を発揮します。ガメイは花崗岩の土壌を好む傾向がありますが、様々な環境に順応できる柔軟性も持ちます。
ソーヴィニヨン・ブラン (Sauvignon Blanc)
ブルゴーニュでは限定的ですが、シャブリの南西にあるグラン・オーセロワ地区のサン・ブリのみで栽培されています。サン・ブリではキンメリジャン土壌でソーヴィニヨン・ブランが栽培され、ソーヴィニヨン・ブラン特有のハーブや柑橘系の香りに、シャブリのミネラル感が加わった独特のスタイルを持ちます。フランスでは「ビストロワイン」として親しまれ、気軽に楽しめるワインとして人気があります。
ブルゴーニュが単一品種でのワイン造りを主体としていることは、その畑の土壌、地形、気候といった「テロワール」の個性が、より純粋かつ明確にワインに表現されることを意味します。これにより、たとえ隣接する畑であっても、土壌の微細な違いがワインの味わいに大きな差異を生み出し、ブルゴーニュのワインは極めて多様性に富んだものとなっています。この純粋なテロワール表現こそが、ブルゴーニュワインの最大の魅力であり、世界中のワイン愛好家を惹きつけてやまない理由なのです。
ブルゴーニュ主要生産地域を巡る旅
ブルゴーニュ地方は南北に長く広がり、その地理的・地質的な多様性から、大きく分けて以下の6つの主要なワイン生産地域に区分されます。各地域は独自のテロワールを持ち、それぞれ異なるスタイルのワインを生み出しています。
シャブリ グラン オーセロワ地区 凛としたミネラル感の白ワイン
ブルゴーニュ地方の最北に位置する飛び地であり、オーセロワ地区ヨンヌ県のシャブリ村に位置し、川と谷が「肋骨のような地形」を形成します。この独特の地形は、ブドウ畑に多様な日照条件と風通しをもたらします。極めて冷涼な気候と、牡蠣の化石を豊富に含むキンメリジャン土壌が特徴です。キンメリジャン土壌はジュラ紀の1億5千万年前の堆積物であり、この特殊な土壌がシャブリワイン特有の「ミネラル感」を生み出す主要因とされています。ただし、標高が低い「プティ・シャブリ」の土壌はキンメリジャン土壌ではなく、より若いポートランディアン土壌であるため、ワインのスタイルも異なります。グラン・クリュ畑は傾斜の急な斜面に位置し、最適な日照と豊かな下土を享受しています。この地域は白ワインで特に有名であり、シャルドネ種からシャープな酸味とミネラル豊富な辛口白ワインが生み出されます。火打石のような鉱物的なニュアンスがシャブリの大きな味の特徴とされています。
シャブリには、プティ・シャブリ、シャブリ、シャブリ・プルミエ・クリュ、シャブリ・グラン・クリュの4段階の格付けが存在します。特にグラン・クリュは生産量がわずか1%に過ぎず、その希少性が際立っています。グラン・クリュには、ブランショ、ブーグロ、レ・クロ(最大面積)、グルヌイユ(「果実感ボタっとジューシー」と評される豊かな果実味)、レ・プルーズ、ヴァルミュール、ヴォーデジール(「標高高いので酸が引き締まっている」とされ、畑が均等なため品質が均一)の7つのクリマ(畑名)があります。ブーグロは西向きで最もコンパクトな味わいとされることが多いです。プルミエ・クリュは40もの畑が存在し、その味わいも多様です。左岸の畑は「酸味がまろやかでジューシーな果実感」が特徴で、「モンマン」はなだらかでジューシーなスタイル、「ヴァイヨン」は急斜面で酸味と引き締まりがある傾向があります。一方、右岸の畑は「酸が強く、引き締まっている」スタイルで、「モンテ・ド・トネール」「モンド・ミリュー」「フルショーム」などが有名です。プルミエ・クリュは丘の名前か畑の名前のどちらかを名乗ることができます。
主に白ワイン(シャルドネ)を生産しますが、コート・ド・セール、トネール、イランシーなどでは赤ワイン(「セザール黒ブドウ」という品種)も作られています。また、サン・ブリ村ではソーヴィニヨン・ブランが栽培されており、キンメリジャン土壌で育つこのワインは、フランスでは「ビストロワイン」として親しまれています。シャブリの食文化としては、エスカルゴとニンニク、グジェール(チーズ風味のシュー生地)が家庭に常備されるのが一般的です。「内陸だから牡蠣はない、外の食材を村に入れないフランス文化」という言葉が示すように、地元の食材を重んじる文化が根付いています。シャブリワインの顕著な特徴である「ミネラル感」は、キンメリジャン土壌と深く関連付けられています。この土壌は、ジュラ紀に形成された牡蠣などの海洋生物の化石を多く含む泥灰質石灰岩で構成されており、水はけが良く、ブドウの根が深く伸び、土壌中の微量なミネラル成分を吸収しやすくなる特性を持つため、ワインに「火打石のような」「潮のような」といった特定の感覚的要素(シャープな酸味、清涼感、硬質な風味)を与えるのです。
コート ド ニュイ地区 赤ワインの聖地が織りなす多様な表情
ブルゴーニュきっての名だたるグラン・クリュが集結する産地であり、赤ワインが9割を占めます。コート・ドール地区の北部に位置し、赤茶色の石灰や小石を含む土壌から力強いスタイルのワインが生まれる傾向があります。村の中央を走る街道の西側にグラン・クリュ、東側にプルミエ・クリュが明確に分かれているのも特徴です。ニュイ・サン・ジョルジュの奥には標高200m~400mのオート・コート・ド・ニュイが広がります。このオート・コート・ド・ニュイは、より冷涼な気候と標高の高さから、引き締まった酸とタンニンを持つワインを生み出します。
-
マルサネ・ラ・コート村
3つの丘に分かれており、日本ではあまり流通していません。しかし、そのワインは「骨格がしっかり」としていながらも「やわらかく」「まろやか」「スムースな味わい」が特徴です。丘がなだらかで等高線の幅が広いため、ブドウが均一に熟しやすく、標高300m地点のワインは「肉付きというより骨格がしっかり、ストラクチャー」と評されます。標高が高い畑では酸味とタンニンがより際立ち、「背骨」のような印象を与えると言われます。プルミエ・クリュには「クロ・デュ・ロワ」や「レ・ロンジュロワ」などがあり、それぞれ異なる土壌の影響を受け、多様なスタイルを生み出しています。この村では、ブルゴーニュでは珍しく、ロゼワインが村名アペラシオンとして認められている産地でもあります。
-
フィサン
ナポレオンが愛したワインとして知られています。村の左右で丘の性質が異なり、特に左側(南)はジュヴレ・シャンベルタンと同じ丘、同じ土壌を持つと言われています。標高350mに位置し、等高線の幅が均一なため、味わいが均一になりやすいですが、その知名度はまだ高くありません。プルミエ・クリュには「ラ・ペリエール」や「クロ・デュ・キャピタル」があり、これらはフィサンの中でも特に凝縮感と複雑性を持つワインを生み出します。東向きの畑が多く、引き締まった味わいが特徴です。「レ・ゼルベレ」は南東向きの畑で、より熟度が高いブドウが収穫され、豊かな果実味を持つワインが生まれます。フィサンのワインは、若いうちはやや閉じた印象がありますが、熟成によって複雑な土のニュアンスやスパイス、熟した果実の香りが開花します。
-
ジュヴレ・シャンベルタン
ブルゴーニュで最も多くの特級畑を擁し、力強くエレガントで長命なスタイルの品格ある味わいが特徴です。ナポレオンが愛したワインとしても有名です。この村には、シャンベルタン、シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ(最古の「クロ」で、その歴史的背景から名前には「シャンベルタン」が付いていません)、シャルム・シャンベルタン、シャペル・シャンベルタン、グリヨット・シャンベルタン、ラトリシエール・シャンベルタン、マゾワイエール・シャンベルタン、リュショット・シャンベルタン、そして最も生産量が少ないクロ・ド・ラ・ロッシュなど9つのグラン・クリュがあります。それぞれのグラン・クリュは微妙に異なる土壌と微気候を持ち、それがワインの個性に反映されます。例えば、シャンベルタンは力強く荘厳なスタイル、クロ・ド・ベーズはより繊細で複雑な香りを持ちます。プルミエ・クリュでは、凝縮感があり等高線幅が狭い「クロ・サン・ジャック」(グラン・クリュに匹敵する品質と評されることもあります)、優しい味わいで等高線幅が広い「ラヴォー(ラヴォー・サン・ジャック)」、そして南東向きでグラン・クリュ昇格間近と評される「カズティエ」が高く評価されています。カズティエは谷の入口に位置するため風がよく抜ける特徴があり、それがワインの複雑性に寄与しています。シャンベルタンの味わいは「赤土土壌(鉄分)」に由来する「骨太でタンニン、スパイシー、ハーブ、味わいしっかり」と評され、力強さと複雑性を兼ね備えています。その他プルミエ・クリュには「シャポネ」や、東向きでグラン・クリュと同じ丘にある「フォントニー」があります。ブロション村の南半分は、ジュヴレ・シャンベルタンを名乗ることができます。
-
モレ・サン・ドニ
畑の面積が狭く、知名度は高くありませんが、グラン・クリュが斜面に位置するため、南北の村(ジュヴレ・シャンベルタンとシャンボール・ミュジニー)の影響を受ける独特のテロワールを持ちます。ニュイ地区では珍しく、「赤と白が認められている」産地です。グラン・クリュには、クロ・ド・ラ・ロッシュ、クロ・サン・ドニ、クロ・デ・ランブレイ、クロ・ド・タール(モノポール)、そしてシャンボール・ミュジニーと共有するボンヌ・マールがあります。「モン・リュイザン」は「コート・ド・ニュイで唯一アリゴテ認証」を受けており、これは昔からアリゴテが植えられていたためです。ドメーヌ・ポンソが有名で、デュジャックやユベール・リニエが三大生産者とされています。「ボンヌ・マール」の約3ヘクタールがモレ・サン・ドニ側にかかり、「熟度が高くフルーツの凝縮感とまろやかな果実味」があり、ジュヴレ・シャンベルタンとは対照的な、より柔らかな味わいです。ダージリンのミルクティーのような香りを持つこともあります。フィサンと同様になだらかな等高線で品質が安定しており、粘土質が多くブドウの粒が大きいので「ジューシーでフルーツ感」があります。モン・リュイザンは全てのクラスの畑を持つものの、認知度が低いため「クロ・ド・ラ・ロッシュを名乗ることが多い」と言われています。アルローの「ル・ミランド」はジュヴレ側の特徴を、「レ・ブランシャール」はモレ・サン・ドニ真ん中の特徴を持つとされます。
-
シャンボール・ミュジニー
この村では赤ワインのみが生産されます。華やかな香りとシルクのように滑らかな飲み心地が最大の魅力で、「エレガンス、気品、フラワリー、女性的でしなやか」と評される優美で可憐な味わいは世界中のワイン愛好家を虜にしています。グラン・クリュはボンヌ・マール(モレ・サン・ドニと共有)と、コート・ド・ニュイで最も高価なグラン・クリュとされる「ミュジニー」です。ミュジニー・グラン・クリュのみ、白ワインの生産が認められている点も特筆すべきです。この白ワインは極めて希少で、世界中のコレクターが探し求める逸品です。「レ・ザムルーズ・プルミエ・クリュ」は、その品質と人気から、他のグラン・クリュよりも高価で取引されることもあるほど評価が高い畑です。土壌は石灰岩土壌がメインで、ブドウの粒が小さく皮が厚いため、「酸の生成が強くなり、酸味が強くエレガントでタンニンもある」ワインが生まれます。若いうちはスミレやバラのようなフローラルな香りが際立ち、熟成とともに複雑なスパイスや土のニュアンスが現れます。「レ・サンティエ」「レ・フュエ」「レ・クラ」はフルーティな傾向があり(モレ・サン・ドニ側)、畑が綺麗に東向きに位置していることが、そのフラワリーな雰囲気を生み出す要因とされています。南に向いている畑では、このフラワリーな雰囲気が出にくいと言われています。
-
クロ・ド・ヴージョ
巨大な石垣に囲まれた印象的な畑で、その石垣があるところだけ空気が異なると言われるほどです(シャンボール・ミュジニーからもその姿を見ることができます)。この石垣は、中世に修道士によって築かれたもので、畑の微気候に影響を与え、ワインの品質に寄与すると考えられています。「レ・プティ・ヴージョ」は白ワインも認められている「レアなワイン」で、流通量が非常に少ないため見つけたら幸運とされます。ミュジニー、レ・ザムルーズ、クロ・ヴージョといった名だたる畑に囲まれているため、「フラワリーな印象」を持ちます。味わいは「フラワリー、スリム、エレガントに骨格がしっかり加わり、ほどよいタンニンと酸味、バランス型」と評され、その調和の取れたスタイルが魅力です。255mの等高線にはタワーがあり、そこから上がVIP(法皇など)に振る舞うワインの境界の目安とされています。リューディ(クリマ)と呼ばれる畑の分割が細かく、200以上の所有者が存在すると言われています。この細分化は、フランス革命による畑の分割が大きく影響しており、品質のばらつきが生じる原因ともなっています。大手ドメーヌは入口に簡単な石垣が表札のようにあり、防犯カメラも設置されているほど、その価値は高いです。ワインを造っていない区画もあり、そのブドウはヴージョのブドウとして高く売られることもあるようです。
-
ヴォーヌ・ロマネ
世界最高峰のワイン「ロマネ・コンティ」が造られる村として知られ、土壌、日当たり、気温の全てがブドウ栽培にとってこれ以上ないという恵まれた条件を備えており、その完璧さから「神に愛される村」と讃えられるブルゴーニュ最高峰の赤ワイン産地です。この村には、ロマネ・コンティ、ラ・ターシュ、リシュブール、ロマネ・サン・ヴィヴァン、グラン・エシェゾー、エシェゾーといった6つのグラン・クリュが名を連ねます。これらのグラン・クリュは、それぞれ独自の個性と複雑性を持ち、世界中のワイン愛好家を魅了しています。「エシェゾー」はグラン・クリュのみがその名を名乗れ、グラン・クリュ以外の畑はヴォーヌ・ロマネまたはブルゴーニュを名乗ります。「レ・ボー・モン」は有名なプルミエ・クリュで南東向きの畑です。「レ・ルージュ」はプルミエ・クリュとグラン・クリュがあり、真東向きです。味わいは「エレガントで女性的」と評され、繊細さと深みを兼ね備えています。レ・ボー・モンはエシェゾー側とロマネ側にあり、プルミエ・クリュも名乗れますが、ボーモンを名乗ることが多いです。谷で風通しが良いため酸味が引き締まる「オー・ブリュレ」と、「典型的な土っぽいキノコ、紅茶、タバコ、ヴィロードのようなヴォーヌ・ロマネ」と評される「レ・シュショ」も評価が高いです。ヴォーヌ・ロマネのワインは、若いうちからキノコ、土、紅茶、タバコといった熟成したような香りが現れることが特徴で、まさに「テロワール」を表現するワインとされます。ファブリス・ヴィゴはテロワール表現に長けた代表的な造り手です。「クロ・パラントゥ」はアンリ・ジャイエの畑(モノポールではありません)で、「100万超え」の価格がつき、「最も偽物が出回るワイン」としてコルクに刻印が開始されたエピソードがあります(ロオジエでコルクを提示しなくてクレームが入った事件も有名です)。「レ・プティ・モン」と「オー・レニョ」も注目されているプルミエ・クリュです。「オー・マルコンソール」「レ・ショーム」も有名です。ミシェル・グロのモノポール「クロ・デ・レア」はクロ・パラントゥを除く最も評価の高いプルミエ・クリュです。「オーレア」「オーラヴィオール」はほぼニュイ・サン・ジョルジュに位置します。食事のペアリングとしては、ジュヴレ・シャンベルタンが4本足のジビエに合うのに対し、ヴォーヌ・ロマネは「ジビエ、特に羽のあるジビエ(鴨、キジ、うずら、雷鳥)」との相性が良いとされます。
-
ニュイ・サン・ジョルジュ
41ものプルミエ・クリュを持つ、広大なアペラシオンです。白ワインも認められています。味わいは「酸味が力強くタンニンはバランスよく香りはエレガンス」、「ボディがしっかりしており飲み応えがある充実感のあるワイン」と評されます。北側(ヴォーヌ・ロマネ側)の畑、例えば「Les Damodes」や「Aux Murgers」はエレガンスなスタイルが特徴で、より繊細なニュアンスを持ちます。これらの畑はヴォーヌ・ロマネに続く丘陵地に位置し、その影響を受けています。中央の畑である「Vignerondes」「Chaignods」「Bousselots」はバランスが良いとされ、等高線がなだらかで、幅広いスタイルを生み出します。南側の畑である「Les Saint-Georges」「Les Cailles」「Les Poirets」「Ronciere」は南東向きの畑で、「力強い酸味、エレガンスな香り、ボディしっかり」という特徴を持ちます。特に「Les Saint Georgeはグラン・クリュ昇格間近」とされており、その品質の高さが注目されています。ジュヴレ・シャンベルタンのボディが「骨格」と例えられるのに対し、ニュイ・サン・ジョルジュは「肉付き=ジューシー」と表現されることがあり、より豊かな果実味と充実感を持つ傾向があります。若いうちは閉じた印象ですが、熟成によって複雑なスパイスや土の香りが現れ、真価を発揮します。
コート・ド・ニュイ地区 まとめ
コート・ド・ニュイ地区は、ブルゴーニュの赤ワインの聖地として、その多様なテロワールが織りなす力強くもエレガントなピノ・ノワールを生み出しています。各村が持つ独自の個性と、グラン・クリュやプルミエ・クリュの畑が表現する複雑な味わいは、ワイン愛好家を飽きさせることがありません。熟成によってその真価を発揮するワインが多く、長期にわたる変化を楽しむことができるでしょう。
コート ド ボーヌ地区 白ワインの銘醸地から生まれる至高の逸品
ロマネ・コンティ、モンラッシェ、ムルソーなど、世界最高峰のAOCを数多く有する地域です。白ワインの生産量が全体の40%と多く、樽をしっかりと効かせたナッティでボリューミーな白ワインを生産する傾向があります。赤・白ともに造られますが、特に白ワインで有名です。
-
オスピス・ド・ボーヌ
「病院」として知られ、毎年11月の第3土曜日から月曜日までの「栄光の3日間」に新酒の祭りが行われます。この祭りは、ブルゴーニュのワイン文化を象徴する一大イベントです。1日目にはクロ・ド・ヴージョの城で晩餐会が催され、2日目にはオスピスでチャリティ・オークション(樽で購入しエチケットに名前が入ります)が行われ、世界中のワイン愛好家が参加します。このオークションの収益は、オスピス・ド・ボーヌ病院の運営資金に充てられ、地域医療に貢献しています。そして3日目にはムルソーでパレードが開催されるなど、地域全体がワインの祭典に沸き立ちます。
-
コルトンの丘
ラドワ・セリニ、アロース・コルトン、ペルナン・ヴェルジュレスの3つの村にまたがる、ブルゴーニュを代表する丘の一つです。この丘は、ブルゴーニュで唯一、赤白両方のグラン・クリュを擁する特別な場所です。コルトン・グラン・クリュは赤ワイン、コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュは白ワインを生産します。
-
ラドワ・セリニ
「真東の畑」が多く、「バランス型」で「パンジェント・スパイシーな印象」を持つワインが特徴です。ピノ・グリ(ピノ・ブーロ)も認められており、30%までブレンド可能です。しかし、グラン・クリュもアロース・コルトンと名乗られてしまうことや、ラベルには「ラドワ・セリニ」と書かれずに「ブルゴーニュ」として表記されることが多いことから、この村の名前でワインを見かけることは少ないかもしれません。これは、アロース・コルトンの知名度が高いため、より市場価値を高めるための戦略的な選択と言えます。11のプルミエ・クリュを持ちますが、その潜在能力はまだ十分に知られていないと言えるでしょう。
-
アロース・コルトン
コルトン・シャルルマーニュ表記のワインは存在せず、グラン・クリュにリューディ(クリマ)の名前をつけることが多いです。「ルナルド」は「急斜面で下は275~上は325mまで」広がり、「バランスが良く」「凝縮感がある」ワインを生み出します。この急斜面は、ブドウに十分な日照を与え、凝縮度を高めます。「ブレッサンド」は「等高線が緩やか」で「フルーツ感重視の赤白」ワインを造ります。「クロ・ド・ロワ」は若干南よりに位置し、力強いワインが特徴です。「ランゲット・プージェット」は良い畑ですが有名ではなく、真南向きのためブドウが熟しすぎてコルトンらしさを失うこともあると言われています。全般の味わいは「ラズベリーやすみれの香り、ソリッドな酸味、骨格があって力強い」と評され、力強さとエレガンスを兼ね備えたワインが多いです。コルトンの丘の赤ワインは、ジュヴレ・シャンベルタンに匹敵する力強さと熟成ポテンシャルを持つとされます。
-
コルトン・シャルルマーニュ
コルトンの丘の西側に位置し、ル・シャルルマーニュとアン・シャルルマーニュの横が谷になっており風が抜けるため、白ブドウの栽培に適しています。この風がブドウの病害を防ぎ、健全な生育を促します。しかし、風が強すぎることでブドウの樹がストレスを受け、「香りが上がってこない気難しいブドウになる」こともあると言われ、その複雑なテロワールがワインの個性につながっています。このワインは、力強いミネラル感と豊かな酸、そして熟成によって現れる蜂蜜やナッツのニュアンスが特徴です。
-
ペルナン・ヴェルジュレス
ピノ・ブーロが30%まで認められている産地です。コルトン・シャルルマーニュに繋がっており、谷で風が抜けるため、味わいは「酸味がシリアスで凝縮感があるブドウ」となります。標高が高いため「酸味もしっかり」しており、フレッシュで引き締まったスタイルが特徴です。アントナン・ギヨンは「全て南向けの畑を所有」し「アルコール分もしっかり」したワインを造る生産者として知られています。このドメーヌのワインは、南向きの畑から得られる完熟したブドウにより、豊かな果実味と力強さを持ちながらも、ペルナン・ヴェルジュレス特有の酸味とミネラル感を保っています。「豊かなタンニンと果実味、肉付きが良い、スパイス」のニュアンスを持つワインが多いです。
-
サヴィニー・レ・ボーヌ
「オー・ヴェルジュレス」は「別格のプルミエ・クリュ」(ペルナン・ヴェルジュレスにまたがる)とされ、「凝縮感、力強い、ストイック、骨格しっかり」とした味わいです。村の中央に川があり左右に分かれ、コルトン側は「凝縮感、ひきしまりストイック」なスタイル、ボーヌ側は「フルーティでジューシー」なスタイルが特徴です。これは、川を挟んで土壌や日照条件が微妙に異なるためです。「レ・ラヴィエール」も人気のプルミエ・クリュです。全般的に「果実味豊かでフルーティー、繊細、エレガント」なワインが特徴で、シモン・ビーズが筆頭生産者として知られています。シモン・ビーズは、このアペラシオンのポテンシャルを最大限に引き出し、エレガントで熟成可能なワインを造ることで高い評価を得ています。
-
ショレイ・レ・ボーヌ
あまり市場に出回っておらず、ブルゴーニュとして出す方が売れる傾向にあるため、村名ワインとして見かけることは少ないかもしれません。「しなやか、シンプル、軽い、優しいワイン」が特徴で、値段も高くないため、気軽に楽しめるブルゴーニュワインとして注目されています。トロボーという女性ワインメーカーが世界に広めようと尽力しており、その努力によって近年評価が高まりつつあります。この村のワインは、その親しみやすさから、日常使いのブルゴーニュワインとして人気を集めています。
-
ボーヌ
フェヴレ、ブシャール、ルイ・ジャドといった大手ネゴシアンのモノポール(単独所有畑)が多い地域です。ボーヌはコート・ド・ボーヌの中心地であり、歴史的な街並みも魅力です。味わいは「なめらかでビロードのようなタンニン、果実味、フルーティ」と評されます。赤白両方のワインが造られており、特にプルミエ・クリュの畑が豊富です。ボーヌのプルミエ・クリュは、その多様なテロワールを反映し、それぞれ異なる個性を持っています。例えば、「ボーヌ・グレーヴ」は力強く熟成向き、「ボーヌ・クロ・デ・ムーシュ」は繊細でエレガントな白ワインで知られています。
-
ポマール
「赤のみ」が生産される産地です。土壌は「赤土土壌 鉄分」が特徴で、この鉄分がワインに独特のミネラル感と力強さを与えます。味わいは「タンニン 骨格 凝縮度」が強く、若いうちは非常に力強いですが、熟成によってそのタンニンが溶け込み、複雑な香りと味わいへと変化します。鴨やジビエとの相性が良いとされます。ボーヌ側はフルーティな傾向があり、ヴォルネイ側はエレガンスで土っぽさ、しなやかさを持つとされます。主要なプルミエ・クリュには「レ・リュジアン」「レ・ゼプノー」「レ・グラン・ゼプノー」などがあり、これらはグラン・クリュに匹敵する品質を持つと評価されています。アルベール・クリポーのモノポールはビストロリストによく見られます。標高240m~300m(基本的なグラン・クリュの標高)に位置し、28のプルミエ・クリュしかありませんが、グラン・クリュに匹敵すると評価されている畑も多いです。
-
ヴォルネイ
味わいは「エレガンスでしなやか、土っぽさがあり素朴なワイン、シンプル」と評されます。ポマール側とムルソー側があり、東向きで均一な畑が多いため、どの畑も味わいが一様になる傾向があります。ポマールが力強い男性的なワインと評されるのに対し、ヴォルネイはより女性的で繊細なスタイルが特徴です。若いうちはラズベリーやスミレのような香りが特徴的ですが、熟成によって複雑な土のニュアンスやキノコ、紅茶の香りが現れます。「サントノ」はヴォルネイとムルソーにまたがる畑で、赤を造ればヴォルネイ、白を造ればムルソーと名乗ることができます。この畑の例からもわかるように、畑の位置関係を把握することがブルゴーニュワインを理解する上で非常に重要であり、ストリートビューで確認することを推奨されるほどです。
-
オート・コート・ド・ボーヌ
モンテリー、オーセイ・デュレス、サン・ロマンなどが含まれる地域で、コート・ド・ボーヌの西側に位置する標高の高いエリアです。1990年頃から知名度が上がってきました。より冷涼な気候と標高の高さから、引き締まった酸とミネラル感を持つワインが多く生産されます。これらのワインは、コート・ド・ボーヌの他のアペラシオンに比べて手頃な価格で、高品質なブルゴーニュワインを楽しめる選択肢として注目されています。
-
モンテリー
ヴォルネイとムルソーの間に位置し、ヴォルネイに近い特徴を持ちます。「フラワリーでバランス良く、スムース、土っぽさ、スパイスさ」が味わいの特徴です。標高が高く酸が強く引き締まった味わいですが、等高線の幅がバラバラで個性があります。南東向きですが地形が複雑なためブドウ栽培が難しいとされます。この複雑な地形が、ブドウに多様な日照条件を与え、ワインの複雑性を高める要因となっています。109ヘクタールが赤ワイン用、白ワインは18ヘクタール(ムルソー側)です。15のプルミエ・クリュがあり、それぞれがこの村の多様なテロワールを表現しています。
-
オーセイ・デュレス
さらに標高が高く、「更に酸味が強く凝縮感」があり、急な斜面なので熟度も高いです。「山のワイン(サン・ロマンも同様)」と呼ばれます。有名生産者としてドメーヌ・ルロワが挙げられます。ルロワがこの村でワインを造ることは、このアペラシオンの潜在能力の高さを示唆しています。果皮が厚くなるため色が濃くタンニンも出ますが、それが溶け込んでいるのが特徴です。ムルソー村の隣に位置し、「細身のムルソー」と評されることもあり、将来的に一級昇格する可能性があるとされています。これは、ムルソーに似た高品質な白ワインを生産できるポテンシャルがあるためです。
-
サン・ロマン
「400mオーバーの標高」に位置し、「Combe(凹んだ地形)」が特徴です。タンニンはきめ細かくスムースで、ベリーの香りが前面に出ます。「引き締まったかんじ、カリッとしたベリー」のような味わいです。急斜面で日照が多く、オーセイ・デュレスと同じく「山のワイン」と呼ばれます。生産者ヴァンサン・ジラルダンは力強いワインを造ることで知られています。彼のワインは、サン・ロマンのテロワールを最大限に引き出し、凝縮感とミネラル感に溢れたワインを生み出しています。オーセイ・デュレスとサン・ロマンのワインは鶏肉(ピジョンなど)に合うとされます。
-
ムルソー
ピュリニー寄りの南側にプルミエ・クリュが集中する、なだらかな地域です。白ワインの銘醸地として世界的に有名です。そのワインは、豊かな果実味とナッツやバターのような香りが特徴で、熟成によってさらに複雑なコクと深みを増します。「クロ・ド・ラ・バル」はコント・ラフォンのモノポールで、市街地にありながらプルミエ・クリュ、グラン・クリュに匹敵する「別格」の評価を受けています。5大プルミエ・クリュとして「グッド・ドール」「ポリュゾ」「ジュブリエール」(一番評価が高く「ザ・ムルソー バランスが良い」とされます)、「シャルム」(柔らかな印象)、「ペリエール」(ゴージャスで酸味が強い、標高が高い)が挙げられます。プルミエ・クリュではないものの「ナルヴォー」「リモザン」「グラン・シャルム」も匹敵する品質を持つとされます(ヴァンサン・ジラルダンなど)。赤ワインも認められていますが(390ヘクタール中10ヘクタール)、ほとんどがヴォルネイ側に位置します。かつてはシェリー、ヘーゼルナッツ、キノコ、樽熟成が特徴でしたが、1997年頃から早期酸化(プレモックス)や質の悪いコルクの流通で評価が下落しました。特に1995年、1996年ヴィンテージが問題となりました。これに対し、バトナージュを増やし酸化防止剤を減らすことで、味わいをフルーツやミネラルに変えていきました。コント・ラフォン、ソゼ、ルフレーヴといった著名なドメーヌも大打撃を受けましたが、これらの努力により、ムルソーのワインは再びその輝きを取り戻しています。赤ワインでは「レ・サントノ」(赤はヴォルネイ・サントノ、白はムルソー・サントノ)が有名です。
-
ピュリニー・モンラッシェ
「0.3%しか赤ワインを生産しない、白の産地」です。17のプルミエ・クリュを持ち、ムルソー側はフルーツ感がある傾向があります。「ピュセル」が最も評価が高く(グラン・クリュの隣)、グラン・クリュに匹敵する品質を持つとされます。モンラッシェは「なにもない山 ハゲ山」と表現されることもあります。味わいは「エレガンス、貴賓(気品)フラワリー、ナッティ、ミネラリィ、スムース、しなやか」と評されます。若いうちは白い花や柑橘系の香りが特徴的ですが、熟成によってヘーゼルナッツやバター、蜂蜜といった複雑なアロマが展開します。全ての畑が南東向きに位置しており、ブドウに最適な日照を与えます。「ブラニィ」は、赤ワインはブラニィ、白ワインはピュリニー・ブラニー、ムルソー・ブラニーと名乗ることができます。
-
シャサーニュ・モンラッシェ
「赤ワインのほうが評価が高い産地」とされます。プルミエ・クリュには「モルジョ」(赤の評価が高い)、「ブドリオット」(赤の評価が高い)、「クロ・サン・ジャン」(赤が有名)、「ショーメ」「ヴェルジェ」などがあります。味わいは「柔らかさ まろやかさ スムース(酸味滑らか) バランスの良さ」が特徴で、魚にも肉にも合う汎用性の高さがあります。若いうちはフレッシュな果実味とミネラル感が特徴ですが、熟成によってより複雑なナッツやスパイスのニュアンスが現れます。「レ・クリオ」がグラン・クリュであることについては裁判沙汰になっている(バタールの生産者が所有していたため)というエピソードがあります。唯一のシャサーニュ側のグラン・クリュです。
-
グラン・クリュ (モンラッシェ系)
-
モンラッシェ: 「帽子を脱いでひざまずいて飲みなさい」と評される、世界最高峰の白ワインです。香りは上がってこないものの「下にたまりにたまっている」「誰も喋らなくなる 完成している」とまで言われます。その複雑性と深遠な味わいは、まさに至高の体験です。
-
シュヴァリエ・モンラッシェ: モンラッシェのすぐ上に位置し、「酸が強い、標高が高い」特徴を持ちます。より引き締まったミネラル感と、シャープな酸が魅力です。熟成によって、より洗練された複雑なアロマが展開します。
-
バタール・モンラッシェ: モンラッシェの東側に位置し、「ふくよか、ボリューム」のある味わいが特徴です。より力強く、豊かな果実味と厚みを感じさせるスタイルです。若いうちから比較的親しみやすいですが、長期熟成によってその真価を発揮します。
-
-
サン・トーバン
ピュリニー・モンラッシェの弟分とされ、「認知は低いが場所はいい」と評されます。区画としては「アン・レミー」が知られ、マルク・コランが有名生産者として挙げられます。マルク・コランは、サン・トーバンのポテンシャルを世界に知らしめた立役者の一人です。ガメイ発祥の地という説もありますが、実際にはガメイは植えられていません。「サン・トーバン・ガメイ」というシャルドネのワインが存在します。30のプルミエ・クリュを持ち、「石灰質土壌」が特徴です。ピュリニー側はナッティな傾向があります。味わいは「豊かさがあって充実感のあるワイン エレガント」とされます。「サン・トーバン アンヴェズヴォ シャトードサントネイ」は元ブルゴーニュ公国初代公王のシャトーで、ビオロジック栽培を行っています。モンラッシェと同じ地層で石灰質が強くミネラルが豊富です。
-
サントネ
石田さんイチオシの産地で、シャサーニュの隣が特に人気です。「クロ・ド・タヴァンヌ」が一番評価が高く、急斜面に位置します。「一様に南東向きでバランスがよい(東向きだとボリューミー)」とされます。標高も高く(300-500m)、ジュヴレ・シャンベルタンと同じ地層であるため、味わいも「スパイシー、凝縮感、鉄分」といった特徴を持ちます。赤ワインは力強く、黒系果実の香りとスパイシーなニュアンスが特徴です。「赤が優勢な産地」です。
-
マランジュ
3つの村に分かれており、「赤が優勢な産地」です。味わいは「優しくて飲みやすくて親しみやすい」と評され、初心者向きです。赤系果実のピュアな香りと、まろやかな酸味が特徴です。魚にも野菜にも合う(グリーンのトーンがあるため)汎用性の高さがあります。「ボーヌ最南端(実際はマランジュ)」に位置します。この地域は、手頃な価格でブルゴーニュワインの魅力を楽しめる隠れた銘醸地として注目されています。
コート・ド・ボーヌ地区 まとめ
コート・ド・ボーヌ地区は、ブルゴーニュの白ワインの銘醸地として、その多様なテロワールから多種多様なシャルドネを生み出しています。赤ワインも生産されますが、白ワインの繊細さ、複雑性、そして熟成ポテンシャルは世界中のワイン愛好家を魅了してやみません。各村の個性を理解することで、より深くブルゴーニュワインの世界を楽しむことができるでしょう。
コート シャロネーズ地区 隠れた名産地の魅力と多様性
コート・ドール地区の南に続く南北約40km、幅4~6kmの細長い丘陵地帯です。北に行くほど石灰岩、南は粘土質と土壌が異なります。この地域は、コート・ドールに比べて価格が手頃でありながら、高品質なワインを生産していることで近年注目を集めています。南北に車で30分、約25kmの距離に主要な村が点在しています。
-
ブーズロン
「白ワインのみ アリゴテのみ」という珍しい産地です。ドメーヌ・ラモネが有名にしたことで知られています。「柑橘の香りとミネラル感シャープな酸味ほどよい果実味」が特徴です。優しい飲み心地で樽も効いています。ユベール・リニエのようなイメージと評されることもあります。55ヘクタールの小さい産地で、9割が同じ苗字の生産者であることも特徴です。これは、この地域が家族経営の小規模生産者によって支えられていることを示しています。
-
リュリー
城があるため「品がある」とされます。ラムロワーズ(常に三星レストラン)のハウスワインにも使用されるほどです。23のプルミエ・クリュを持ち、「白ワインの産地」ですが、赤ワインも半分ほど生産されます。ピュリニー・モンラッシェ寄りで「華やかさ フローラルでミネラル エレガンス 酸がある」味わいが特徴です。赤ワインは「白ワイン的個性がでる赤ワイン 透明感があって酸味が優しい」と評され、タンニンも優しく、酸味が伸びやかです。南東向きの畑が多く、クレマン・ド・ブルゴーニュ発祥の地でもあります。
-
メルキュレイ
フェヴレが有名にした産地で、「シャロネーズ最大の生産量を誇るAOC」です。「赤の産地」ですが、白ワインも少量生産されます。味わいは「骨格しっかりタンニン、力強い、熟成感もある」とされます。白ワインは「赤の特徴が出る白ワイン(リュリーの逆)力強さとボディ」を持ちます。2016年が良い年(コート・ド・ボーヌが良かった年)で、2017年はコート・ド・ニュイの年でした。フェヴレはメルキュレイから始まったドメーヌです。「ニュイサンジョルジュに似た力強い味わい」と評されることもあります。
-
ジヴリィ
38のプルミエ・クリュを持ち、南東向きの赤ワインの産地です。白ワインもありますが、赤ワイン寄りの味わいです。味わいは「赤系フルーツのピュアな香り 酸味はまろやか コンパクトでチャーミング」で、初心者向きとされます。セガン・マニュエルは力強さが出ているワインを造りますが、本来はもっと柔らかい味わいです。「ブルボン王朝でアンリ4世が愛飲したことで知られる歴史のある生産地。丸みのある優しい味わい」が特徴です。
-
モンタニィ
「白のみの産地」です。49のプルミエ・クリュを持ちます。味わいは「ムルソーのような味わい 熟成感果実味厚み密っぽさ熟度フルーティーさ」と評されます。ロレンソンのモンタニィは特にムルソーっぽさが出ているとされます。「最大のPremiere Crus面積を誇る白の産地」であり、シャブリと同じ特徴のキンメリジャン土壌もあるのが特徴です。
マコネ地区 シャルドネの故郷が育むフルーティーなワイン
ブルゴーニュ地方の南部に位置し、ブルゴーニュの中で最もブドウ栽培面積が広い生産地区です。生産されるワインの約70%がシャルドネを使用した白ワインであり、「シャルドネの故郷」とも呼ばれ、ブルゴーニュ地方で生産される白ワインの約1/3を生産しています。「半地中海性気候」のため「トロピカルフレーバー、熟度が上がるので貴腐っぽくなる」特徴があります。甘口ワインも作られており、ル・ブルテはヴィレ・クレッセの甘口ワインで知られています。マコネ地区の象徴的な風景として、ヴィレ・クレッセにあるソルトレイ(とんがり)とヴェルジソン(フラット)という二つの岩山が挙げられます。これらは「Deux Roche(二つの岩)」と呼ばれ、この地域の独特な土壌と地形を象徴しています。
ワインの等級としては、マコン、マコン・ヴィラージュ、そして村名クラスのプイィ・フュイッセ、サン・ヴェラン、ヴィレ・クレッセなどがあります。サン・ヴェランでシャルドネを造ればサン・ヴェラン、ガメイを造ればサントムール(隣接)と名乗ることができます。プイィ・フュイッセは谷になっていて風が抜けるため「酸が引き締まる」特徴があります。特にプイィ・フュイッセはマコネで最も評価が高く、「ジャック&ナタリー・ソメーズ プイィ・フュイッセ シュール・ラ・ロッシュ」は「岩盤の上。20cm下は石灰岩の岩盤。マコンにありながらモンラッシェの風格を持つ。プルミエ・クリュ昇格間近の別格畑」と評されています。「ドメーヌ・ルフレーヴ マコン・ヴェルゼ」はビオディナミ栽培を行っています。
ボージョレ地区 ガメイの魅力を最大限に引き出す多様なスタイル
ブルゴーニュ地方の最南端に位置し、南北に約55kmにわたって広がる細長いワイン産地です。「半大陸性気候」です。北側にクリュ、南側に広域とヌーヴォーが集中します。北側は花崗岩で斜面で、より凝縮感のあるワインを生み出します。一方、南側は砂岩粘土質でフラットな地形であり、軽やかでフルーティーなワインが多く生産されます。
-
ムーラン・ナ・ヴァン
村名ではありませんが、風車がある地域で赤い土(鉄分を多く含んだ花崗岩)が特徴です。「一番タンニンがしっかり骨格があるワイン」とされ、ボージョレ・クリュの中でも最も力強く、長期熟成のポテンシャルを秘めています。
-
フルーリー
「花畑が広がる村=観光名所」として知られ、その名の通り、ガメイらしい「華やかでフルーティ、非常に飲みやすいワイン」が特徴です。バラやスミレのようなフローラルな香りが際立ち、軽やかな口当たりで、プーレロティ(鶏のロースト)がメジャーな料理とされます。
-
コート・ド・ブルイィ
ブルイィ山がある地域で、この山の火山性土壌がワインに独特のミネラル感と骨格を与えます。「濃厚で力強いワイン」が造られ、クリュ・ボージョレの中でも比較的しっかりとした味わいです。
-
モルゴン
「ふくよかでボディ豊か、丸みのある仕上がり」が特徴です。熟成によってピノ・ノワールを思わせるような複雑な香りが現れることから、「ブルゴーニュのモルゴン」と称されることもあります。ボージョレの中でいち早くBioやナチュラルなワイン造りを始めた村でもあります。
ブルゴーニュ独自の格付けシステムとその意味
ブルゴーニュは、フランスのAOC(原産地統制名称)の約1/4を占めるほど、その格付けシステムが非常にユニークで細分化されています。ボルドーがシャトー(生産者)ごとに格付けされるのに対し、ブルゴーニュは「畑(クリマ)」ごとに格付けされるのが最大の特徴です。この格付けは、地域のテロワール(地理的特徴)が大きく反映されており、畑ごとの微細な違いがワインの品質と特徴に大きな影響を与えるため、ブルゴーニュワインの多様性と複雑性の根源となっています。この複雑な格付けを理解することが、ブルゴーニュワインの奥深さを知る第一歩となるでしょう。
4つの主要な格付け
ブルゴーニュワインの格付けは、品質と希少性のピラミッドを形成しています。下から上に行くほど、生産量が少なくなり、品質が高く、価格も高くなる傾向があります。
-
地域名ワイン (Régionale)
最も一般的な格付けであり、ブルゴーニュ全域で収穫されたブドウから生産されます。ブルゴーニュ全体の生産量の約53%を占め、最も生産量が多く、希少性は低いですが、日常的に楽しめるワインとして親しまれています。品質は飛び抜けて高いものは少ないですが、飲みやすく、ブドウ品種の個性を感じられるワインが多いです。ラベルには「BOURGOGNE」と記載されます。手頃な価格でブルゴーニュワインの入門として最適です。
-
村名ワイン (Village)
特定の村で収穫された様々な畑のブドウをブレンドして造られます。ブルゴーニュ全体の約35%または36%を占めるボリュームゾーンです。それぞれの村は独自のテロワール特性を持ち、それがワインに反映されます。例えば、ジュヴレ・シャンベルタン村のワインは力強く、シャンボール・ミュジニー村のワインはエレガントといった具合です。ラベルには村の名前のみが記載されます。このクラスから、各村の個性やテロワールの片鱗を感じ取ることができます。
-
プルミエ・クリュ (Premier Cru / 1er Cru)
グラン・クリュに次ぐ格付けであり、特定の村内にある一流の畑から生産されます。ブルゴーニュ全体の生産量の約10%を占め、希少性が高いです。これらの畑は、適度な日照、理想的な土壌条件、優れた排水性を持つ斜面に位置しており、ブドウが均一に成熟し、複雑でバランスの取れたワインを生み出します。村名ワインよりもさらにテロワールの個性が明確に表現され、長期熟成のポテンシャルも持ちます。ラベルには村の名前と畑の名前が記載され、例えば「シャブリ・プルミエ・クリュ モンマン」のように表記されます。
-
グラン・クリュ (Grand Cru)
ブルゴーニュで最も高い評価を受ける格付けであり、特定の単一畑から生産されます。生産量はブルゴーニュ全体のわずか約1.4%または2%と、極めて希少です。これらの畑は、最適な日照条件と排水性の良い土壌を持つ南東向きの斜面に位置しており、ブドウの成熟に理想的な環境を提供します。これにより、ワインは深い色合いと極めて複雑な風味、そして非常に長い熟成能力を持つことが特徴です。グラン・クリュのワインは、その畑のテロワールが最大限に表現された、まさに「芸術品」と評されます。生産量が限られているため非常に高価であり、その品質と希少性から世界中のワイン愛好家やコレクターに高く評価されています。ロマネ・コンティのように数千万円の値が付くものも存在します。ラベルには畑の名前だけが記載されます(例:「ロマネ・コンティ」や「モンラッシェ」)。
畑の格付けだけですべてが決まるわけではなく、生産者の技術や、その年の気候(ヴィンテージ)もワインの味わいに大きな影響を与えます。同じグラン・クリュであっても、生産者やヴィンテージによって異なる表情を見せるのが、ブルゴーニュワインの奥深さであり、愛好家を惹きつける理由の一つです。
伝統と革新が息づくワイン醸造の哲学
ブルゴーニュのワイン造りは、小規模で分散した畑の特性を深く理解し、各地域のテロワールを最大限に引き出す醸造技術と熟成プロセスを通じて行われることを基本としています。多くの生産者にとって、「テロワールの表現のためには近代的アプローチよりも伝統的な手法が適している」という考え方が根底にあります。これは、土地の個性を尊重し、ブドウ本来の力を引き出すことを重視するブルゴーニュの哲学を反映しています。
伝統的な醸造は、土地の個性を尊重する哲学に基づいています。ブドウ栽培からワイン醸造までを一貫して手掛ける「ドメーヌ」と呼ばれる作り手が多いのは、畑の個性を最大限に引き出すための伝統的なアプローチです。彼らは、それぞれの畑の土壌や微気候を熟知し、それに合わせた栽培方法や醸造技術を適用します。天然酵母を使用する生産者も多く、これはブドウと畑に元々存在する微生物の力を借りて、より自然な発酵を促すためです。これにより、ワインにその土地ならではの複雑なアロマと味わいがもたらされると考えられています。また、オーク樽での熟成もブルゴーニュワインの特徴であり、新樽の使用比率や熟成期間は、ワインのスタイルやテロワールに合わせて慎重に調整されます。
伝統を重んじる一方で、ブルゴーニュの生産者は現代の課題に対応し、品質をさらに向上させるために革新的なアプローチも積極的に取り入れています。アンリ・ジャイエがもたらした低温マセレーションは、今日ではブルゴーニュの優良生産者のほとんどが何らかの形でこの技術を取り入れています。これは、発酵前にブドウを低温で浸漬することで、色素やアロマ成分を穏やかに抽出し、ワインの味わいを強くしつつ、なめらかな口あたりを出すことを狙う手法です。この技術は、ワインに深みと複雑性を与えながらも、過度な抽出を避け、エレガントさを保つことに貢献しています。
ビオディナミや有機農法への転換も顕著です。ドメーヌ・ルフレーヴは1996年には全ての畑をビオディナミに転換し、世界トップクラスの評価を確立しました。ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ(DRC)も2007年には全面的にビオディナミ栽培に移行しています。これらの農法は、化学肥料や農薬の使用を避け、自然環境を尊重し、土壌の活力を高めることで、ブドウ樹がより健全に育ち、テロワールを最大限に表現することを目指すアプローチです。これにより、ワインの純粋性と複雑性がさらに高まると考えられています。
近年、気候変動はブルゴーニュの伝統品種にとって脅威となっており、特にシャルドネが危機に直面しているとの指摘もあります。気温の上昇はブドウの成熟を早め、酸度の低下やアルコール度数の上昇につながる可能性があります。これに対し、DRCでは、気候変動の影響を受けて収穫時期を早めたり、収穫したブドウを低い温度で保つ冷却装置を導入したり、収穫の時間帯を朝6時から午後2時までに限定したりするなど、柔軟に対応しています。これらの取り組みは、ブドウの鮮度と酸度を保ち、ブルゴーニュワイン本来のエレガントなスタイルを維持するための努力です。このように、ブルゴーニュの生産者は、伝統的な哲学を守りつつも、常に新しい技術やアプローチを取り入れ、ワインの品質向上とテロワールの表現に尽力しています。
ブルゴーニュワインの未来と不朽の魅力
ブルゴーニュワインは、その類稀な「テロワール」の概念を核とし、何世紀にもわたる歴史の中で培われた独自の文化と生産体制を築き上げてきました。単一品種主義は、ピノ・ノワールとシャルドネが持つテロワール表現能力を最大限に引き出し、隣接する畑でさえ異なる個性を持つワインを生み出します。この多様性と複雑性こそが、ブルゴーニュワインが世界中のワイン愛好家を惹きつけてやまない最大の理由です。
ブルゴーニュのワイン醸造は、伝統的な手法を継承しつつも、ビオディナミ栽培、低温マセレーション、気候変動への対応といった現代的な革新を積極的に取り入れています。この伝統と革新の融合が、品質の安定化と、より複雑で多様なスタイルのワインの創出を可能にし、かつて「悪いヴィンテージ」とされた年でも高品質なワインを生み出すに至っています。これは、ブルゴーニュワインが過去の栄光に安住することなく、常に進化し続ける姿勢を示しています。生産者たちは、ブドウ畑の健全性を保ち、自然との共生を目指すことで、未来へと続くワイン造りの道を切り開いています。
世界最高峰のワインを数多く生み出すグラン・クリュに代表される厳格な格付けシステムは、「畑」の個性を絶対的な価値として評価するブルゴーニュ独自の哲学を具現化しています。このシステムは、ワインの品質と価値の根拠を明確にする一方で、消費者がワインを理解するための深い知識を要求します。しかし、その知識を深めることで、一本のワインが持つ物語や背景をより深く味わうことができるようになります。
ブルゴーニュワイン産業は、地域経済、文化、観光において不可欠な存在です。ワインツーリズムは地域に経済効果をもたらし、世界中から訪れる観光客を魅了しています。国際市場における高い輸出額は、ブルゴーニュワインが世界中のワイン愛好家から継続的に支持されていることを示しています。特に日本市場は、ブルゴーニュワインにとって重要な輸出先であり続けており、日本におけるブルゴーニュワインの人気は非常に高いです。
ブルゴーニュワインの不朽の魅力は、単なる高品質な飲料という枠を超え、その土地の歴史、文化、そして生産者の情熱が凝縮された芸術作品である点にあります。テロワールへの深い敬意と、伝統を守りながらも革新を恐れない精神が、ブルゴーニュワインを「生きる伝説」として未来へと繋いでいくでしょう。ブルゴーニュワインを味わうことは、単にワインを飲むだけでなく、その土地の魂と歴史を感じる体験となるのです。

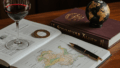

コメント