目次
自然派ワインへの高まる関心とその真実
近年、私たちの食生活において「健康」や「自然」への意識が非常に高まっています。特に、口にするものに対する安全性や透明性を求める声が大きくなり、添加物の少ない食品や飲料への関心が増しています。このような背景の中で、自然派ワイン、通称ナチュラルワインは、その独特な製法や環境への配慮といったコンセプトから、「体に良い」というイメージを伴い、大きな注目を集めています。しかし、その健康上の利点が科学的にどの程度裏付けられているのかについては、まだ十分な理解が進んでいないのが現状です。
本記事では、自然派ワインの健康効果について、科学的根拠に基づき徹底的に検証します。これにより、皆様がワインを選ぶ際に、より賢明な判断ができるよう、客観的で詳細な情報を提供することを目指します。
自然派ワインとは何か?一般的なワインとの違いを深く理解する
自然派ワインの健康への影響を考察する上で、まずその基本的な定義と、一般的なワインやオーガニックワインとの明確な違いを深く理解することが不可欠です。
自然派ワインの定義と特徴
自然派ワインは、ブドウの栽培からワインになるまでの全工程で、できる限り自然な方法を追求して造られるワインを指します。その哲学は、ブドウ畑の生態系を尊重し、ブドウ本来の生命力を最大限に引き出すことにあります。栽培においては、化学肥料や合成農薬を一切使用せず、有機栽培やビオディナミ農法が採用されるのが一般的です。これにより、土壌の健康が保たれ、ブドウの根が深く張り、その土地特有のミネラルを吸収しやすくなると考えられています。手作業での収穫は、ブドウを傷つけることなく、最適な熟度のものだけを選別することを可能にします。また、単一品種の大量栽培ではなく、多様なブドウ品種を育てることで、ブドウ畑の生物多様性を高め、病害のリスクを自然な形で低減させる努力も行われます。こうした栽培方法を通じて、ブドウ本来の個性が最大限に引き出されることが目指されます。
醸造においては、人工的な培養酵母ではなく、ブドウの皮や醸造所に自然に付着している野生酵母(天然酵母)を使って自然発酵させます。これにより、ワインに複雑で個性豊かな香りと風味が生まれるとされています。また、酸化防止剤として広く使われる二酸化硫黄(亜硫酸塩、SO2)などの添加物は、ごく少量しか使わないか、全く使わない場合もあります。清澄剤(卵白やゼラチンなど)を使ったり、ワインを透明にするためのろ過をしたりすることも極力避けるため、ブドウが持つ本来の風味や、その土地ならではの「テロワール」が色濃く反映された、非常に個性的な味わいのワインが生まれます。テロワールとは、土壌、気候、地形、そしてその土地に根付く伝統など、ブドウが育つ環境の総合的な個性を指す言葉です。これらの製法は、ワインの「生きている」状態を保ち、時間とともに変化する複雑な風味を楽しむことを重視しています。
「ナチュラルワイン」と「自然派ワイン」は、それぞれ英語と日本語の違いであり、同じ概念を表す言葉として用いられています。フランス語では「ヴァン・ナチュール」とも呼ばれ、世界中でこの哲学に基づいたワイン造りが広がりを見せています。
一般的なワインやオーガニックワインとの違い
自然派ワインと一般的なワインの製法には、いくつかの顕著な違いが存在します。一般的なワインの生産では、効率性と安定性を追求するために、ブドウ畑で化学肥料や農薬が広範に使用されることが多く、大規模な単一品種栽培や機械化された管理が一般的です。これは、収量や品質の安定性を重視し、市場の需要に応えるための合理的な選択とされています。
醸造方法においても、一般的なワインでは発酵を安定させるために商業酵母が使用され、品質を均一化するために酸化防止剤(二酸化硫黄)や様々な調整剤(酸味料、タンニン、着色料など)が加えられます。また、ろ過や清澄が積極的に行われ、クリアで安定した仕上がりが重視されます。これにより、どのボトルを開けても同じような味わいが保証され、消費者の期待に応えやすくなります。
味わいと特徴の面では、自然派ワインは野生酵母による発酵や無添加の醸造法により、果実感が豊かで酸味やミネラル感が際立つなど、独特の風味が特徴です。一方で、添加物を抑えるため、味わいのばらつきや酸化のリスクを伴うことがあります。これに対し、一般的なワインは、安定した品質とバランスの取れた味わいが魅力であり、万人受けするフルーティーで滑らかな仕上がりが特徴です。
「オーガニックワイン(ビオワイン)」も自然派ワインと混同されやすいですが、両者には重要な違いがあります。オーガニックワインは、有機栽培されたブドウから作られたワインを指し、ナチュラルワインと同様に化学物質や合成物質を使用しない製法が特徴です。しかし、両者の最大の違いは「専門の認証機関によって認証されているか否か」にあります。日本では「オーガニックワイン」に対してのみ、有機JAS認定という公的なルールが存在し、この認定基準では、一部の農薬使用や規定内の亜硫酸塩の添加も認められています。これに対し、自然派ワインには統一された厳格な国際的な認証制度が存在しないため、その定義や品質は生産者によって大きく異なる場合があります。
この認証制度の不在は、自然派ワインの品質や製法に多様性をもたらす一方で、消費者が「自然派」という言葉から抱く健康に関するイメージと、実際の製品の間に乖離を生じさせる要因となり得ます。消費者は「無条件に健康的」あるいは「より安全」といった直感的な印象を抱きやすいですが、統一された基準がないため、個々の製品の特性を正確に把握することが難しい場合があります。この定義の曖昧さは、後に述べる健康上の主張や潜在的なリスクに関する誤解の温床となる可能性を秘めており、健康に関する情報を受け取る際には、より批判的な視点を持つことの重要性を示唆しています。
「体に良い」とされる理由と科学的根拠の検証 掘り下げた考察
自然派ワインが「体に良い」と言われる背景には、主に添加物の少なさや特定の成分への期待があります。しかし、これらの主張が科学的にどの程度裏付けられているかについては、詳細な検証が必要です。
亜硫酸塩(SO2)の含有量と健康への影響の深掘り
自然派ワインは、酸化防止剤として広く用いられる亜硫酸塩(二酸化硫黄、SO2)の添加量が極めて少ない、あるいは全く無添加であることが多いため、「体に良い」「二日酔いしにくい」「頭痛が起きにくい」といった認識が広まっています。
亜硫酸塩は、ワインの酸化を防ぎ、色や風味の劣化を遅らせるだけでなく、ワイン中の微生物の繁殖を抑えるという不可欠な役割を担っています。ワインは空気に触れると酸化し、酢酸菌などの微生物が増殖することで品質が著しく損なわれる可能性がありますが、亜硫酸塩はこれを効果的に防ぎます。また、亜硫酸塩はワインの醸造過程で自然に発生する成分でもあり、人為的に添加しなくてもブドウの皮や発酵過程で微量が含まれています。各国では亜硫酸塩の最大許容量が厳しく定められており、例えばEUでは40ppmから160ppm、アメリカや日本では350ppmが最大許容量とされています。世界保健機関(WHO)も、体重1kgあたり0.7mgを1日の推奨摂取量としています。
適切な量の亜硫酸塩は、ほとんどの人にとって無害であるとされています。しかし、喘息を持つ方や亜硫酸塩に対するアレルギー体質の方にとっては、低濃度であっても発作やアレルギー反応を引き起こす可能性があります。具体的には、気管支の収縮、蕁麻疹、吐き気、下痢などの症状が報告されています。このため、EUでは、二酸化硫黄を10mg/L以上含むワインには「Contains Sulfites(亜硫酸塩含有)」の表示が義務付けられており、消費者がアレルギーのリスクを認識できるよう配慮されています。
二日酔いや頭痛への影響 真実と誤解の解明
多くの消費者がワインによる頭痛や二日酔いの原因を亜硫酸塩に結びつけがちですが、この認識は科学的な裏付けが十分ではありません。マスターオブワインであるソフィー・パーカー・トムソンの研究によって、「ワイン不耐性」(頭痛や体の不調)の主因は「生体アミン」であり、特にヒスタミンが主要な原因物質であることが特定されました。この研究は、頭痛の原因が亜硫酸塩含有や酸化防止剤とは直接関係がないことを示唆しています。
むしろ、亜硫酸塩の添加を極力避ける自然派ワインの製法は、有害な微生物の増殖を阻害する酸のレベルが低くなりがちであり、結果として生体アミンの発生率が大幅に上がると考えられています。生体アミンは、アミノ酸の代謝から生まれる有機化合物で、ヒスタミンやチラミンなどがその代表です。これらは体内で多様な生理作用を担いますが、過剰に摂取すると、血管の拡張や血圧変動、吐き気、ほてり、頭痛といった不調を引き起こす可能性があります。特に、天然酵母で発酵させたワインは生体アミンが多くなる傾向があり、乳酸菌がヒスタミン、チラミン、カダベリン、プトレシンといった様々な生体アミンを生成し、これらが不調の原因となることがあります。培養された乳酸菌の中には生体アミンの生産量が少ないものも存在しますが、自然派ワインで用いられる天然の乳酸菌ではその量が多くなることがあります。
二日酔いの主要な原因は、ワインの種類に関わらず、アルコールの過剰摂取とそれによって体内で生成されるアセトアルデヒドの蓄積です。アセトアルデヒドはアルコールが肝臓で分解される際に生じる有害物質で、吐き気、頭痛、倦怠感などの二日酔いの症状を引き起こします。自然派ワインが二日酔いを軽減するという主張については、現時点では決定的な科学的根拠は出ていません。最終的に、ワインによる不調を避けるためには、適量を守って楽しむことが最も重要であると結論付けられます。
消化酵素や農薬残留物に関する考察の深掘り
自然派ワインの健康効果に関する別の主張として、自然酵母で発酵させることでワインに独特の風味と香りが加わり、消化を助ける酵素が多く含まれるという見解があります。これにより、消化器系の健康維持に寄与するとされています。確かに、発酵食品には様々な酵素が含まれていますが、これらの酵素がワインを介して人体に摂取された際に、消化器系に具体的な健康効果をもたらすかについては、さらなる詳細な研究が求められます。ワイン中の酵素は、胃酸などの影響で活性を失う可能性も考慮に入れる必要があります。
一方で、自然派ワインが有機農法で栽培されたブドウを使用している点は、健康上の明確な利点と言えます。合成農薬を使用しないため、ワインに農薬の残留物が含まれるリスクが低減され、結果として消費者の健康リスクが軽減される可能性があります。一般的な農薬には、神経毒性を持つものや内分泌かく乱作用を持つものなど、長期的な健康影響が懸念されるものも存在します。有機栽培は、これらの化学物質への曝露を減らすという点で、環境と人体双方への配慮を示す側面が非常に強いです。
この状況は、「添加物が少ない=体に良い」という直感的な結びつきが、必ずしも科学的な真実と一致しないことを示唆しています。消費者が「より自然なもの」を求める心理は理解できますが、品質の安定性や安全性を確保するためには、ある種の「介入」が不可欠である場合もあります。自然派ワインの製法は、意図せず不調の原因となる物質を増加させる可能性があり、健康に関する情報に接する際は、単一の要素だけでなく、製法全体が人体に与える影響を多角的に評価することが重要です。消費者は「自然派」というラベルだけで判断せず、個人の体質や感受性を考慮に入れる必要があります。
自然派ワインに潜む可能性のあるリスク 詳細な分析
自然派ワインの製法は、その魅力であると同時に、特定の健康リスクや品質上の課題を内包する可能性も指摘されています。
生体アミン(ヒスタミンなど)と不調の関連性
前述の通り、自然派ワインは、天然酵母や乳酸菌の使用、そして酸化防止剤である亜硫酸塩の添加量を極力抑える製法により、ヒスタミンやチラミンといった生体アミンの含有量が高くなる傾向があります。これらの生体アミンは、ワイン不耐性の主因とされており、摂取量によっては頭痛、吐き気、ほてり、動悸、発疹などの症状を引き起こす可能性があります。特に、生体アミンを少量しか生産しない培養乳酸菌が存在する一方で、自然派ワインで用いられる天然の乳酸菌では生体アミンの量が多くなることがあると報告されています。個人の生体アミン分解酵素の活性には差があり、この酵素の活性が低い人は、少量の生体アミンでも不調を感じやすい傾向にあります。
微生物汚染と品質のばらつきの具体的な問題
亜硫酸塩はワインの酸化防止だけでなく、有害な微生物の繁殖を抑える殺菌剤としての役割も果たします。そのため、亜硫酸塩の添加を極力抑える自然派ワインは、雑菌の影響を受けやすく、品質が不安定になったり、望ましくないワインが出来てしまう可能性が低くありません。
実際に、ワインの試飲会などでは、極端な酸化(シェリーのような香り)、還元(硫黄化合物によるゴムや卵のような香り)、カビ臭(湿った段ボールのような香り)、微生物汚染(ブレットと呼ばれる馬小屋のような香り、またはマウス臭と呼ばれるポップコーンのような香り)、予期せぬ瓶内二次発酵(泡立ち)など、いわゆる「欠陥」と呼ばれる状態のワインが、一般的なワインよりも高い割合で散見されることがあります。これらの欠陥は、ワインの風味を著しく損なうだけでなく、場合によっては健康に影響を及ぼす可能性も否定できません。また、ワインの保存状態が不適切である場合、特に高温や乾燥はワインの劣化を早め、食中毒の原因となる微生物の増殖を促す可能性があります。コルクの劣化や不適切な開封方法も、ワインが微生物に汚染されるリスクを高める要因となります。
ただし、ワインが人体に有害な影響を及ぼすような微生物の影響を受ける場合、ほとんどのケースでは、その前にワインの味や香りに明らかな欠陥臭として異常が現れることが多いとされています。これは、消費者がワインの異常に気づく手がかりとなり得ます。しかし、自然派ワイン特有の濁りや独特の風味を「個性」と捉える傾向があるため、場合によってはそれが微生物汚染の兆候である可能性も見過ごされがちです。このため、消費者は自然派ワインを選ぶ際に、単に「自然派」という表示に頼るだけでなく、そのワインの状態(香り、色、沈殿物など)を注意深く確認し、異常があれば飲用を避けるといった、より慎重なアプローチが求められます。これは、消費者の情報リテラシーの向上と、生産者側による製品情報の透明性確保の重要性を示しています。
ワイン全般における健康的な飲酒の原則 普遍的な視点
自然派ワインに特化した健康効果が限定的であるという検証結果を踏まえると、ワインの種類にかかわらず、健康的な飲酒習慣を確立することが最も重要であるという結論に至ります。
適量飲酒の重要性 厚生労働省・WHOのガイドラインの再確認
厚生労働省は、節度ある適切な飲酒量を1日あたり「純アルコール約20g」と定めています。これは、一般的なワイン(アルコール度数12%程度)であれば、約1杯半(120mlあたり純アルコール12g)に相当する量です。ビール(5%)であれば中瓶1本(500ml)、日本酒(15%)であれば1合(180ml)に相当します。世界保健機関(WHO)も、過度な飲酒が健康リスクを高めることを警告しており、肝臓への負担を考慮し、週に1~2日の休肝日を設けることを強く推奨しています。また、WHOは亜硫酸の1日の推奨摂取量を体重1kgあたり0.7mgと定めており、これは体重50kgの人で35mg、60kgの人で42mgに相当します。
結局のところ、二日酔いやその他の健康被害の根本的な原因は、ワインの種類に関わらず「飲みすぎ」にあります。アルコールの過剰摂取は、肝臓病、心血管疾患、特定の癌、神経系の障害など、様々な健康問題のリスクを高めます。健康を維持するためには、常に適量を守ることが最も重要です。
ポリフェノールとその他の健康効果のさらなる詳細
ワイン、特に赤ワインには、健康に良いとされる成分が豊富に含まれています。その代表的なものがポリフェノールです。ポリフェノールには、レスベラトロール、アントシアニン、カテキンなど様々な種類があり、これらは強力な抗酸化作用と抗炎症作用を持つことが知られています。日本の国立健康・栄養研究所とサントリーの共同研究により、赤ワインに含まれるポリフェノールが動脈硬化を予防する効果があるとする研究が発表されています。ポリフェノールは、色調が濃いワインや、チリのカベルネ・ソーヴィニヨンやオーストラリアのシラーズなど、温暖な産地で収穫されたブドウから作られた凝縮感のあるワインに多く含まれる傾向があります。
また、「フレンチパラドックス」(飽和脂肪酸の摂取量が多いにもかかわらず、フランス人の心臓病死亡率が低い現象)の一因として、赤ワインの摂取が挙げられることもあります。ただし、この現象はワインだけでなく、食生活全体やライフスタイルなど、様々な要因が複合的に作用していると考えられており、ワイン単独の効果として過度に期待すべきではありません。
さらに、ワイン摂取が認知症のリスクを低減する可能性を示唆する研究も存在します。特に女性や喫煙者において、ワイン摂取群で認知症のリスクが低いという関連性が報告されていますが、これはあくまで関連性であり、因果関係を証明するためにはさらなる研究が必要です。白ワインにも健康効果が指摘されていますが、赤ワインと同様に飲みすぎは避けるべきです。
飲酒時の注意点と休肝日の徹底
健康的にワインを楽しむためには、飲酒量だけでなく、飲み方にも細心の注意を払う必要があります。アルコールは肝臓で分解されるため、肝臓への負担を軽減するためには、空腹時の飲酒は避け、料理と一緒に楽しむのが良い飲み方とされています。食事を摂ることでアルコールの吸収が緩やかになり、血中アルコール濃度が急激に上昇するのを防ぐことができます。飲酒中は、体内のアルコール濃度を薄め、脱水症状を防ぐために、こまめに水を飲むことが推奨されます。飲んだアルコール量と同等かそれ以上の水を飲むのが効果的です。
長期的な健康維持のためには、週に1~2日の休肝日を設けることが不可欠です。これにより、肝臓がアルコール分解から回復する時間を確保し、肝機能の低下を防ぐことができます。さらに、21時以降の飲酒は太りやすくなるだけでなく、睡眠の質を低下させる可能性があります。アルコールは一時的に眠気を誘いますが、深い睡眠を妨げ、夜中に目が覚めやすくなるなど、睡眠の質を低下させることが知られています。また、夜遅くの飲酒は、消化器系への負担も大きくなります。
ワイン飲用後の口腔ケアも健康維持の重要な側面です。ワインを飲むと口内が酸性になり、歯の表面のエナメル質が一時的に脆くなるため、飲用直後の歯磨きはエナメル質を傷つける「酸蝕歯」のリスクを高める可能性があります。そのため、飲用後10~15分程度時間を空け、水で口をゆすいでから、できれば柔らかめのブラシで歯磨きを行うことが推奨されます。
誇大広告と消費者の誤解に注意する 倫理的側面と法的規制
自然派ワインの人気が高まるにつれて、その健康上の利点に関する主張が、しばしば科学的根拠を欠いた誇大広告に繋がりやすいという問題が浮上しています。これは消費者保護の観点からも重要な課題であり、倫理的な問題もはらんでいます。
科学的根拠の不足とマーケティング表現の課題
自然派ワインが「二日酔いを軽減する」「頭痛が起きにくい」「体が軽くなる」といった主張は、現時点では科学的なエビデンスが不足しており、決定的なデータは得られていません。これらの主張は、主に個人の感覚や推測に基づいていると考えられます。にもかかわらず、「亜硫酸無添加だから健康に良い」「生きたワインだから体に優しい」といった表現を用いて販売されているケースが散見されます。これは、消費者が「無添加=健康的」「より安全」と誤認しやすい心理を利用したマーケティング手法と言えます。このような表示は、消費者の期待を不当に高め、製品の真の特性を誤解させる可能性があります。
景品表示法と消費者保護の重要性 規制とペナルティ
消費者を欺くような「嘘や大げさな表示」は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)によって厳しく規制されています。誇大広告の具体例としては、「表示された効能がでたらめだった」という苦情が多数寄せられた事例や、実際には追加料金がかかるにもかかわらず、あたかも表示された料金だけでサービス全てを受けられるかのように有利に見せる表示などが挙げられます。また、「No.1表示」や「今だけ半額」といった強調表現も、その根拠が曖昧な場合は法的リスクを伴い、消費者庁はこれらの広告に対する監視を強化しています。
特に注意すべきは、広告であることを隠して行われる、いわゆる「ステルスマーケティング」です。これは2023年10月1日から景品表示法違反の対象となりました。事業者が広告であることを明示せずに商品やサービスを宣伝した場合、消費者を誤解させる行為として厳しく取り締まられます。景品表示法に違反した場合、事業者には措置命令(表示の改善や再発防止策の実施命令)や高額な課徴金納付命令(違反行為によって得た不当な利益相当額の徴収)が科され、企業の信用失墜に繋がる可能性があります。健康に関する誇大広告は、病気を持つ人々が本来受けるべき適切な治療の機会を逸してしまうおそれがあるため、特に深刻な問題として認識されています。消費者の「健康志向」と「自然志向」は、科学的根拠の乏しい健康主張を伴う自然派ワインのマーケティングを助長し、結果的に誤解や不当表示のリスクを高めている状況が見られます。消費者は、マーケティングメッセージに惑わされず、科学的根拠に基づいた情報を見極める能力を養うことが重要です。
結論 自然派ワインとの賢い付き合い方と今後の展望
本レポートの検証を通じて、自然派ワインが「体に良い」という一般的な認識について、多角的な側面からその科学的根拠を評価しました。
自然派ワインの魅力と現実のバランス
自然派ワインは、化学肥料や農薬を使わない栽培、野生酵母による自然発酵、そして添加物の最小限化といった製法により、ブドウ本来の個性を引き出し、その土地のテロワールを表現するユニークな魅力を持っています。環境保護への配慮という点でも、その価値は高く評価できます。これらの点は、持続可能な農業や食文化を重視する現代において、非常に意義深いものです。
しかし、「体に良い」「二日酔いしにくい」「頭痛が起きにくい」といった健康上の主張については、科学的根拠が不足しているか、むしろ生体アミンの増加などによる不調のリスクがあることが示されました。特に、頭痛の主要因が生体アミンであることが明らかになり、亜硫酸塩の低減が必ずしも頭痛の軽減に繋がらないという事実が示されています。自然派ワインの魅力は、その「自然」な製法から生まれる多様な風味や、生産者の哲学にあり、健康効果を第一に求めるべきではないと言えるでしょう。
最も重要なのは「適量」と「飲み方」の徹底
ワインの種類が自然派であるか否かにかかわらず、健康的な飲酒における最も重要な原則は、厚生労働省やWHOが推奨する「純アルコール約20g/日」という適量を厳守し、週に1~2日の休肝日を設けることです。二日酔いや健康被害の根本原因は、アルコールの過剰摂取にあります。どのようなワインであっても、飲みすぎは健康に悪影響を及ぼすという普遍的な事実を忘れてはなりません。
また、空腹時を避け、食事とともに水を飲みながら楽しむこと、そして飲酒後の適切な口腔ケアも、健康的な飲酒習慣を維持するために不可欠な要素です。これらの飲酒習慣は、ワインの健康効果を最大限に引き出し、同時にリスクを最小限に抑えるための基本となります。
消費者への提言と未来への示唆
これらの分析を踏まえ、自然派ワインと上手に付き合い、賢く楽しむための具体的な提言を以下にご紹介します。
-
過度な期待をしない: 自然派ワインを「万能薬」であるかのような過度な健康効果を期待せず、その製法がもたらすユニークな味わいや個性を楽しむ視点を持つことが重要です。ワインはあくまで嗜好品であり、その本質的な価値は風味や文化的な側面にあります。
-
情報を批判的に評価する: 「無添加だから安全」「健康的」といった単純なフレーズに惑わされることなく、科学的根拠に基づいた情報を求める姿勢が求められます。特に健康に関する主張には慎重になり、公的機関や信頼できる専門家の情報を参照することが賢明です。インターネット上の情報だけでなく、専門家の意見や学術的な研究結果に目を向けることが大切です。
-
自身の体質を理解する: ワインによる不調(頭痛、アレルギーなど)は個人差が大きく、亜硫酸塩だけでなく生体アミンなど様々な要因が関与します。自身の体質やワインに対する反応を理解し、無理のない範囲で楽しむことが大切です。もし特定のワインで不調を感じる場合は、そのワインのタイプや製法について調べてみるのも良いでしょう。
-
品質の確認: 自然派ワインは、その製法上、品質のばらつきがある可能性も指摘されています。購入時や飲用前に、ワインの状態(香り、色、濁り、コルクの状態など)を注意深く確認し、異常があれば飲用を避ける判断も必要です。信頼できる販売店やソムリエに相談することも、品質の良い自然派ワインを選ぶ上で役立ちます。
自然派ワインは、その哲学と個性的な味わいにおいて、ワイン愛好家にとって非常に魅力的な選択肢です。しかし、健康上の利点に関しては、一般的なワインと同様に「適量を守り、賢く楽しむ」という原則が最も重要であると言えます。消費者が科学的根拠に基づいた知識を持ち、自身の健康を第一に考えながらワインを楽しむことが、真に豊かなワインライフに繋がるでしょう。

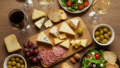

コメント