目次
赤ワインテイスティングの第一歩 外観評価の重要性
ワイン愛好家の皆様、グラスに注がれた赤ワインを前にした時、その色合いや輝きに隠された物語を感じたことはありますか?実は、ワインの外観は、その品質や熟成度、さらにはブドウ品種や生産者の意図までをも雄弁に語りかけています。テイスティングの最初のステップである外観評価は、まさにワインが持つ『秘密の言葉』を解き明かす鍵なのです。その中でも「外観」の評価は、テイスティングの最初の段階であり、ワインの特性に関する重要な手がかりを与えてくれます。この最初の視覚的な分析は、その後の香りの評価や味わいの分析に先立ち、ワインの全体像を予測するための基礎を築くものです。
外観からは、ワインの熟成度、使用されているブドウ品種、フレーバーの密度、酸度、ボディ、そして健全性など、多岐にわたる情報が読み取れます。例えば、深く不透明な色は、フルボディでタンニンの豊富な、温暖な気候の赤ワインを連想させ、香りを嗅いだり味わったりする前に、潜在的なブドウ品種やスタイルを絞り込む手助けとなります。逆に、淡くレンガ色がかった赤ワインは、熟成が進んでいるか、あるいは皮の薄い品種であることを示唆します。このように、ワインの外観から得られる視覚的な手がかりは、一種の予備的な診断ツールとして機能し、テイスターが初期の仮説を立て、その後の嗅覚的・味覚的評価でそれを検証または修正することを可能にします。この予測能力は、特にブラインドテイスティングのシナリオにおいて非常に価値があり、テイスターが品種や産地の候補を絞り込み、その後の香りと味わいの評価をより的確に進めるための強力な手助けとなります。これにより、テイスティングプロセス全体をより効率的かつ情報に基づいたものにすることができるでしょう。
例えば、グラスに注がれた瞬間に、そのワインが若々しいのか、それとも長年の熟成を経てきたのか、おおよその見当をつけることができます。また、特定のブドウ品種が持つ典型的な色合いを知っていれば、その色から品種の候補を絞り込むことも可能です。この初期段階での情報収集は、その後の香りの複雑さや味わいのバランスを評価する上で、非常に重要な「羅針盤」となるのです。専門家や熱心な愛好家にとって、外観を正確に表現するための専門用語を習得することは、テイスティングコメントの精度を高め、他者との円滑なコミュニケーションを可能にする上で不可欠です。
ワインの透明感と輝き 清澄度と輝きの見極め方
清澄度(Clarity)は、ワイン中に浮遊物や澱がない透明度を指します。透明であるほど、ワインは「澄んでいる」と表現されます。一方、輝き(Brilliance)は、ワインがどれほど明るく、光沢があるように見えるかを指し、しばしばワインの酸度と関連しています。高い清澄度と輝きは、一般的にワインの品質と醸造における丁寧さを示す指標となります。
日本語表現
-
澄んだ (Clear): 赤ワインの外観に明らかな異常がない場合の標準的な選択肢です。ソムリエ試験などでは、判断に迷った場合にこの表現を選ぶことが推奨されます。これは、ワインが適切に醸造され、安定していることを示唆する最も基本的な健全性の指標だからです。
-
輝きのある (Brilliant/Sparkling): 若々しく、活気に満ちた外観を示す際に用いられます。光を反射してキラキラと輝く様子を表現し、ワインのフレッシュさや高い酸度を示唆することが多いです。基本となる表現ですが、熟成が感じられるワインには、より落ち着いた光沢を示す「落ち着いた」が使われることもあります。
-
深みのある (Deep/Profound): 明らかに色が濃く、凝縮感のあるワインに対して選択されることがありますが、「澄んだ」が無難な選択肢とされています。これは、色の濃さ自体が清澄度を妨げるものではないため、透明性が確保されていれば「澄んだ」がより適切であるためです。
-
落ち着いた (Settled/Calm): 熟成感のあるワインの外観を表現する際に用いられ、若々しいワインの「輝きのある」と対比されます。熟成により色素が安定し、光沢が穏やかになった状態を指します。
英語表現
-
Brilliant: 浮遊物や澱が全くなく、完全に透明なワインの外観を指します。文字通り「輝かしい」と形容されるような、完璧な透明度と光沢を持つ状態です。
-
Clear: 透明であることを示します。Brilliantほどではないものの、視覚的な障害がない状態です。
-
Limpid: クリスタルクリアで、「Brilliant」と同義であり、ワイン生産における高品質と注意深さを示唆します。非常に澄み切っていて、まるで水のように透明な印象を与えます。
-
Cloudy: コロイド状の濁りや微粒子が存在することを示し、ワインの不健全性や欠陥を示唆する場合があります。酵母の残骸、バクテリアの活動、タンパク質の凝固、あるいは不適切な清澄化や濾過が原因となることがあります。
-
Dull: 明らかなコロイド状のヘイズ(濁り)があり、浮遊粒子によって光が反射することで確認できます。光沢がなく、くすんだ印象を与える状態です。
両言語ともにワインの透明度と光沢の概念を扱いますが、英語の「Brilliant」や「Limpid」は、視覚的な完璧さと高い品質、しばしば丁寧な醸造や濾過の有無を強く示唆する含意を持っています。日本語の「輝きのある」も品質を示唆しますが、単に「光沢がある」というより広い意味で使われることもあります。この微妙なニュアンスの違いは、プロフェッショナルなコミュニケーションにおいて正確性を期す上で重要です。英語の用語は絶対的な粒子の不在に重点を置く傾向があるのに対し、日本語の用語は全体的な活気も考慮に入れる場合があるという、強調点の違いが浮き彫りになります。
高い清澄度と輝きは、一般的に健全で丁寧に造られたワインであることを示唆しますが、一部の無濾過ワインでは意図的にわずかな濁りが見られることもあります。例えば、自然派ワインの中には、風味を最大限に引き出すために意図的に濾過を行わないものがあり、その結果として微細な澱やタンパク質が残ることがあります。しかし、明らかな濁り(cloudiness)は、ワインの欠陥や腐敗の兆候である可能性があります。これは、微生物の活動によるものや、不適切な保存状態によるタンパク質の凝固などが考えられます。また、酸度が高いワインは、しばしばより強い輝きを放ちます。これは、酸がワインの安定性を高め、光の透過性を良くするためと考えられています。
ワインの個性を示す色の濃淡と色調
色の濃淡
色の濃淡は、ワインの色がどれほど薄いか、あるいは濃いかを示すもので、特定の色調(例:ルビー、ガーネット)とは区別されます。これは、ワインのボディや醸造過程における抽出度に関する重要な情報を提供します。
日本語表現 (JSA)
-
無色に近い (Almost Colorless): 赤ワインでは稀ですが、濃淡の一般的な表現として存在します。非常に淡いロゼワインや、極めて色の薄い赤ワインに限定的に用いられることがあります。
-
淡い (Pale): 明るい赤ワインに用いられます。白ワインの濃淡の選択肢でもあります。ピノ・ノワールやガメイなど、皮の薄いブドウ品種のワインによく見られます。
-
明るい (Bright): 赤ワインの濃淡が淡い場合に特に用いられる表現です。光をよく透過し、軽やかな印象を与えます。
-
やや明るい (Slightly Bright): 淡いと中間の中間の濃淡を示します。
-
やや濃い (Slightly Dark): 赤ワインの濃淡において、無難な選択肢とされています。多くの赤ワインがこの範囲に収まるため、判断に迷った際に選びやすい表現です。
-
濃い (Dark/Deep): 色が非常に凝縮されており、光をあまり透過しない状態です。カベルネ・ソーヴィニョンやシラーなど、皮が厚く色素の豊富な品種に見られます。
-
非常に濃い (Very Deep): 極めて色が濃く、ほとんど光を通さないほど不透明な状態を指します。新世界のマルベックや、非常に凝縮感のあるシラーズなどに見られます。
英語表現 (WSET & General)
-
Pale: 色が薄いことを指します。光を透過しやすく、グラスの底がはっきりと見える程度の濃さです。
-
Medium: 中程度の濃淡です。多くの一般的な赤ワインがこの範疇に入ります。
-
Deep: 非常に濃縮された色合いです。グラスの底がやや見えにくい、あるいはほとんど見えないほどの濃さです。
-
Opaque: 非常に濃く、向こう側が全く見えないほど不透明であることを指し、シラーやマルベックのような非常に凝縮されたワインに用いられます。光を完全に遮断するような、漆黒に近い色合いを表現します。
一般的に、濃い色調はフルボディでタンニンの豊富なワインを示唆し、醸造中のスキンコンタクト(果皮との接触)が長いことを意味します。このスキンコンタクトの期間が長いほど、果皮に含まれる色素(アントシアニン)やタンニンがワインに多く抽出されるため、色が濃くなり、味わいも力強くなります。淡い色調は、ライトボディのワインや、皮の薄いブドウ品種(例:ピノ・ノワール)を示唆します。これらの品種はもともと色素が少ないため、淡い色合いになる傾向があります。ワインが色素を失う速度は、その熟成能力を示唆します。商業的なワインは、長期熟成を意図したワイン(10~14年)よりも早く色を失う傾向があります(2~4年)。これは、長期熟成に耐えるワインは、色素がより安定しており、ゆっくりと変化していくためです。
濃淡は、単なる物理的な特性に留まりません。それは、醸造家がマセラシオン期間やキャップマネジメントといった工程で下した決断、さらにはブドウ品種、気候、成熟度、収穫量といったブドウ栽培の要因を雄弁に物語っているのです。例えば、温暖な気候で育ったブドウや、日照量が豊富な年のブドウは、色素が豊富で濃い色合いのワインになる傾向があります。大胆で抽出感のあるスタイルを目指す醸造家は、スキンコンタクトを最大化し、深い色合いのワインを造ります。逆に、ボージョレ・ヌーヴォーのような軽めのスタイルは、スキンコンタクトを最小限に抑えるため、淡い色合いになります。これは、濃淡が生産者の意図するスタイルやヴィンテージの状況を示す窓口となり、ワインの潜在的な構造と風味のプロファイルに関する重要な初期の手がかりを提供するということを意味します。
色調
色調は、ワインの具体的な色合いを指し、その熟成度やブドウ品種に関する重要な情報を提供します。
日本語表現 (JSA)
-
ルビー (Ruby): 紫がかった淡い赤色。2018年からは「ラズベリーレッド」と同義とされています。若々しく、フレッシュな印象を与え、ピノ・ノワール、ガメ、マスカット・ベーリーAなどの品種に適しています。
-
ガーネット (Garnet): 紫がかった濃い赤色。2018年からは「ダークチェリーレッド」と同義とされています。ルビーよりも色が深く、カベルネ・ソーヴィニョン、シラーなどの品種に適しています。若々しいながらも凝縮感のある印象を与えます。
-
レンガ (Brick): オレンジがかった赤色。熟成が進んだワインに見られる色調です。色素が分解され、酸化が進むことで現れる色で、熟成による複雑性を示唆します。
-
ラズベリーレッド (Raspberry Red): 2018年に追加された新しい用語で、従来の「ルビー」と同じ意味です。より具体的な果実の色を連想させることで、テイスターにイメージを伝えやすくしています。
-
ダークチェリーレッド (Dark Cherry Red): 2018年に追加された新しい用語で、従来の「ガーネット」と同じ意味です。こちらも、より具体的な果実の色を例に出し、深い赤色を表現しています。
-
オレンジ(グリ)を帯びた (Orangish (Gris)): 2022年に追加された新しい用語で、一部の甲州ワインに見られるような、かすかなオレンジ色を帯びた色調を表現します。甲州の果皮のピンク色に由来し、フランス語のgris(灰色)にちなんでいます。これは、特定の品種の特性をより細かく捉えるための進化を示すものです。
英語表現 (WSET & General)
-
Purple: 非常に若いワインに見られる色で、青みがかった/紫がかった色合いを示します。フレッシュで、まだ熟成のポテンシャルを秘めていることを示唆します。ボージョレ・ヌーヴォーなどに典型的な色です。
-
Ruby: 若い赤ワインによく見られる色合いで、しばしば強烈な赤・黒系果実の風味を伴います。WSETでは、Purpleの次に現れる色として、熟成の初期段階を示します。
-
Garnet: 熟成が進み、複雑さが増したワインに見られる、暖かみのある秋のような赤色です。WSETでは、Rubyの次に現れる色として、熟成の中期段階を示します。
-
Tawny: ほとんど茶色に近い色で、長期熟成(しばしば数十年)したワインや、ポートワインのような酒精強化ワインに見られます。完全に酸化が進んだ状態を示し、ドライフルーツやナッツのような熟成香を伴うことが多いです。
-
Brick: 「Tawny」と同様に、熟成を示唆します。オレンジがかった茶色に近い色合いです。
-
Magenta: 紫がかった赤色で、若いカベルネやシラーの縁によく見られます。鮮やかで力強い印象を与えます。
-
Purple-Black: 非常に不透明で、若いシラー/シラーズ、ムールヴェードル、マルベックなどに見られます。色素が非常に豊富で、光をほとんど通さないほどの濃い色合いです。
同じ用語(「ルビー」、「ガーネット」)が、WSET(国際基準)とJSA(日本基準)のどちらに従うかによって、熟成度と濃淡に関して根本的に異なる意味合いを持つという事実は、バイリンガルなワインの文脈で活動する者にとって極めて重要な点です。WSETでは熟成の進行(Purple → Ruby → Garnet → Tawny)を示すのに対し、JSAでは若い、紫がかったワインの濃淡(ルビー=淡い、ガーネット=濃い)を示すために使用されます。この相違は、文脈(JSAかWSETか)が明確に理解されていない場合、重大な誤解を招く可能性があります。例えば、JSAの基準で「ガーネット」と表現されたワインをWSETの基準で評価すると、熟成が進んだワインと誤解される可能性があります。特にプロフェッショナルな環境では、ワインの外観について議論する際に、どの基準を用いているかを明示することの重要性を強調しています。JSAが「ラズベリーレッド」や「ダークチェリーレッド」といった新しい用語を導入したことは、彼らのシステムを明確化または洗練しようとする試みであると考えられますが、中心的な違いは依然として存在します。
ここで、WSETとJSAの赤ワインの色調表現における具体的な違いを、以下の表で詳しく比較してみましょう。この表は、それぞれの用語が持つニュアンスと、それが示すワインの特性を一覧で理解するのに役立ちます。
赤ワインの色調表現 日本語と英語の比較
| カテゴリー | 日本語用語 (JSA) | 日本語での意味/説明 | 英語相当語 (General/WSET) | 英語での意味/説明 | 典型的なワイン/熟成度 | JSAとWSETの相違点に関する注記 |
|
若いワイン |
ルビー |
紫がかった淡い赤 |
Ruby |
若い赤ワインの基本色。しばしば強烈な赤・黒系果実の風味を伴う。 |
ピノ・ノワール、ガメ、マスカット・ベーリーA (JSA) / 若いカベルネ・ソーヴィニョン、メルロー (WSET) |
JSAでは若いワインの淡い色、WSETでは熟成初期の色。 |
|
ガーネット |
紫がかった濃い赤 |
Garnet |
熟成が進み、複雑さが増したワインに見られる、暖かみのある秋のような赤色。 |
カベルネ・ソーヴィニョン、シラー (JSA) / 熟成が進んだ赤ワイン (WSET) |
JSAでは若いワインの濃い色、WSETでは熟成中期の色。 |
|
|
ラズベリーレッド |
旧来のルビーと同じ。紫がかった淡い赤。 |
Ruby (equivalent) |
– |
ピノ・ノワール、ガメ、マスカット・ベーリーA |
JSAの新用語。 |
|
|
ダークチェリーレッド |
旧来のガーネットと同じ。紫がかった濃い赤。 |
Garnet (equivalent) |
– |
カベルネ・ソーヴィニョン、シラー |
JSAの新用語。 |
|
|
紫がかった |
若いワインの縁に見られる色合い。 |
Purple |
非常に若いワインに見られる、青みがかった/紫がかった色合い。 |
ボージョレ・ヌーヴォー、非常に若いシラー |
JSAの補助的用語。WSETの最も若い色。 |
|
|
黒みを帯びた |
明らかに黒みがかったワインに。 |
Purple-Black |
非常に不透明で、縁の色の変化がほとんどない。 |
マルベック、シラーズ、ムールヴェードル |
JSAの補助的用語。 |
|
|
オレンジ(グリ)を帯びた |
ほとんど無色だがかすかにオレンジ色を帯びた色調。 |
Orangish (Gris) |
– |
一部の甲州ワイン |
JSAの新用語。 |
|
|
熟成ワイン |
レンガ |
オレンジがかった赤。 |
Brick |
熟成したワインの色。 |
熟成した赤ワイン、サンジョヴェーゼ、テンプラニーリョ、ネッビオーロ |
JSAの熟成色。WSETのGarnet/Tawnyに相当。 |
|
– |
– |
Tawny |
ほとんど茶色に近い色。長期熟成(しばしば数十年)したワインや酒精強化ワイン。 |
ポートワイン、非常に古い赤ワイン |
WSETの最も熟成した色。JSAには直接の同等語なし。 |
グラスに現れるワインの粘性 脚や涙が語ること
粘性(Viscosity)は、ワインがグラスにどれだけ付着するか、その濃度や豊かさを示すものです。フランス語では「Jambe(ジャンブ)」とも呼ばれます。グラスを傾けて元に戻した際に、グラスの内側にワインが伝って落ちてくる跡が「脚(Legs)」または「涙(Tears)」と呼ばれます。
日本語表現
-
粘性が高い/低い (High/Low Viscosity): ワインの粘り気の程度を直接的に表現します。粘性が高いほど、ワインはよりとろみがあり、重厚な印象を与えます。
-
脚 (Legs): グラスの内側を伝うワインの跡を指します。脚の数、太さ、落ちる速度によって、ワインの粘性を評価します。
-
涙 (Tears): 「脚」と同義で用いられることもあります。詩的な表現として使われることもあります。
-
脚/涙が多い/少ない (Many/Few Legs/Tears): 跡の数や持続性で粘性の高さを評価します。脚が多い、または太く、ゆっくりと落ちるほど、粘性が高いと判断されます。
-
ディスク (Disk): ワインの液面を横から見たときに観察できる層を指します。ディスクが厚いほど粘性が高いと判断されます。これは、ワインの表面張力と液体自体の密度によって形成されるものです。
英語表現
-
Viscosity: 液体がどれだけ粘り気があるか、半流動的であるかを示す性質です。ワインの「ボディ」や「口当たり」に直結する要素です。
-
Legs: ワインをグラスで回したときに、グラスの内側を流れ落ちる液体の筋を指します。これは「マランゴニ効果」と呼ばれる物理現象によるもので、アルコールの蒸発速度が水よりも速いため、表面張力の差が生じ、ワインがグラスの壁を這い上がり、その後重力によって液滴となって落ちてくるものです。
-
Tears: 「Legs」と同義です。
-
Disk: ワインを横から見たときの液面に見える層を指します。
アルコール度数や糖度が高いワインほど粘性が高くなり、「脚」や「涙」がより多く、長く現れる傾向があります。これは、アルコールが水よりも蒸発しやすい性質を持つため、グラスの表面張力によってワインが一時的に上へ引き上げられ、やがて重力でゆっくりと液滴となって流れ落ちる『マランゴニ効果』と呼ばれる現象によるものです。例えば、アルコール度数が14%を超えるようなフルボディの赤ワインでは、はっきりと太く、ゆっくりと流れる脚が見られることが多いです。一方、アルコール度数が低いライトボディのワインでは、脚は細く、すぐに流れ落ちる傾向があります。
脚や涙の観察は、単にアルコールや糖度を示すだけでなく、ワインの口当たりにおける「ボディ」や「重さ」の視覚的な手がかりを提供します。はっきりとした脚が見られるワインは、よりリッチで、実体があり、潜在的に「フルボディ」である可能性が高いです。これは、テイスティングする前にワインの質感や全体的な豊かさを予測するための重要な要素であり、テイスターが口に含む前にワインの印象を形成するのに役立ちます。粘性が高いワインは、口に含んだ際に舌の上でとろりとした感触や、より重厚な存在感を与えることが期待されます。
熟成のサイン 縁の色合いと変化を読み解く
「縁(エッジ)」は、グラスを傾けたときにワインの液面がグラスの縁に接する部分を指します。この部分の色合いを観察することで、ワインの熟成度や、時にはブドウ品種、酸度に関する重要な洞察が得られます。
日本語表現 (JSA)
-
紫がかった (Purplish): 若いワインの縁に見られる色合いです。鮮やかで、まだ熟成が進んでいないことを示唆します。
-
オレンジがかった (Orangish): 熟成段階に入ったワインの縁に見られる色合いで、サンジョヴェーゼ、テンプラニーリョ、ネッビオーロなどの品種でよく見られます。色素のアントシアニンが酸化・分解されることで、この色合いが現れます。
-
黒みを帯びた (Blackish): マルベックやシラーズのように、明らかに黒みがかったワインの縁に用いられます。非常に色素が濃いワインに見られる特徴です。
-
縁が明るい (Bright Rim): 上記のいずれにも該当しない場合に選択されることがあります。特に熟成が進んでいない、標準的な赤ワインの縁に用いられる表現です。
英語表現
-
Rim Variation: グラスの縁に沿ったワインの色の帯の幅と色を指します。この帯の広さや色の変化の度合いが、熟成の進行度を示唆します。
-
Magenta tinged edge: 若いカベルネやシラーの縁に見られるマゼンタ色です。鮮やかで、紫に近い赤色を表現します。
-
Orange/Brown tinged: 熟成したワインを示します。時間の経過とともに色素が変化し、オレンジや茶色がかった色合いになることを指します。
-
Wide rim variation: 熟成したワインを示します。縁の色の変化が大きく、退色した帯が広いほど、熟成が長く進んでいることを意味します。
-
Tight rim variation: 非常に若いワインを示します。縁の色の変化が少なく、本体の色とほとんど変わらない状態です。
-
Slight blue tinge: 赤ワインの縁にわずかな青みがかった色合いがある場合、高い酸度を示唆します。これは、アントシアニンとワイン中の酸の相互作用によるものです。
若い赤ワインの縁は、通常、紫やマゼンタの色合いを示します。これは、アントシアニンと呼ばれる色素がまだ酸化されていない状態であるためです。赤ワインが熟成するにつれて、縁の色は退色し、レンガ色、オレンジ色、または茶色へと変化します。これは、時間の経過とともに色素(アントシアニン)が分解され、またタンニンと結合してより大きな分子を形成し、沈殿していくためです。縁の色の変化の幅(退色した帯の幅)も熟成度を示します。幅が広いほど熟成が進んだワイン、狭いほど若いワインです。例えば、長期熟成型のボルドーワインやバローロなどでは、熟成が進むにつれて縁に幅広いオレンジ色の帯が見られるようになります。
特定のブドウ品種は、若いワインであっても特徴的な縁の色を示すことがあります。例えば、メルローは若いワインでも縁にわずかなオレンジ色を帯びることが多く、ピノ・ノワールはもともと色が淡く、熟成するとレンガ色になります。また、サンジョヴェーゼやネッビオーロといった品種は、比較的若いうちから縁にオレンジ色やレンガ色を帯びる傾向があり、これは品種の特性として知られています。赤ワインの縁にわずかな青みがかった色合いは、高い酸度を示唆します。これは、ワイン中の酸が色素の安定性に影響を与え、特定の光の反射を生み出すためと考えられています。
ワインの縁は静的なものではなく、その色は鮮やかな紫/マゼンタからレンガ/オレンジ/トーニーへと変化する、ワインの酸化熟成プロセスの視覚的なタイムラインとして機能します。これにより、テイスターはワインの履歴を知らなくても、その熟成度を推測することができます。さらに、あまり知られていないが価値のある二次的な手がかりとして、高い酸度を示す「わずかな青みがかった色合い」があります。これは視覚的な手がかり(縁の色)を主要な味覚特性(酸度)に直接結びつけ、ワインの新鮮さや構造に関する早期の手がかりを提供し、フードペアリングや熟成能力の評価において非常に重要です。
ワインの健全性を示す澱の知識と対処法
澱(おり、Ori)は、時間の経過とともにワインボトル底部に沈殿する固形物質を指します。これは醸造および熟成過程における自然な副産物であり、必ずしも品質の低下を示すものではありません。むしろ、一部のワイン、特に無濾過や無清澄で造られたワインにとっては、健全性の証であるとさえ言えます。
日本語表現
-
澱 : 最も一般的な用語です。ワインのボトルやグラスの底に見られる固形物を指します。
-
澱引き (Soutirage): 清澄なワインを別の容器に移し替えることで澱を取り除く作業を指します。これは、熟成中のワインを別の樽に移し替える際などに行われる伝統的な醸造工程の一つです。
英語表現
-
Sediment: 固形粒子の一般的な用語です。ワインの底に溜まる全ての固形物を指します。
-
Dregs: 「Sediment」の別称です。やや口語的な表現で、底に残ったカスのようなニュアンスを含みます。
-
Lees: 特に、発酵後に残る酵母の死骸を指し、澱の構成要素の一つです。Lees contact(澱との接触)は、ワインに複雑性や旨味を与える醸造技術として知られています。
-
Tartrate Crystals / Wine Diamonds: 酒石酸の結晶で、澱のもう一つの一般的な構成要素です。ワインを低温にさらすと析出しやすく、無害です。見た目がダイヤモンドのように見えることから「ワインダイヤモンド」とも呼ばれます。
-
Beeswing: 古い瓶詰めポートワインに見られる薄い膜状の澱です。タンニンや色素が重合してできるもので、非常に繊細な構造をしています。
-
Racking / Soutirage (French): 澱を取り除くプロセスを指します。日本語の「澱引き」に相当します。
澱は、ブドウの皮、果肉、種子、酒石酸塩、酵母、バクテリアなど、様々な有機および無機化合物で構成されています。これらの成分は、ワインの醸造過程で自然に生じるものであり、澱は摂取しても完全に安全です。特に熟成した赤ワインや無濾過/無清澄のワインによく見られ、タンニンの分解や最小限の介入による醸造の結果として形成されます。無濾過のワインは、風味成分を最大限に残すために意図的に澱を除去しないため、澱が多く見られる傾向があります。
澱を摂取しないためには、ボトルを立ててしばらく休ませた後、ゆっくりと注ぐことが推奨されます。これにより、澱がボトルの底に沈殿し、ワインを注ぐ際に混ざりにくくなります。デキャンタージュは、特に熟成ワインから澱を取り除くための最良の方法です。デキャンタージュを行う際は、ワインをゆっくりとデキャンタに移し、澱がボトルに残るように注意深く行います。この際、光源(ろうそくや懐中電灯など)をボトルの首元に当てて、澱が流れ出てくるのを目視で確認しながら注ぐのが一般的です。デキャンタージュは、ワインを空気と接触させて「開かせる」(アロマや風味を引き出す)効果もありますが、澱の除去という点でも非常に重要です。
欠陥どころか、特に熟成した赤ワインにおける澱の存在は、肯定的な指標となり得ます。それは、ワインが自然な風味と香りを保つために最小限の介入(無濾過/無清澄)を受けていること、あるいはタンニンが自然に重合して沈殿するほど十分な瓶内熟成を遂げたことを示唆しています。これは、単なる見た目の透明性よりも、自然な表現と長寿に焦点を当てた醸造哲学を暗示しています。したがって、澱を理解することは、単に物理的特性を観察するだけでなく、醸造家の意図やワインの旅路を認識することへと鑑賞のレベルを高めます。また、デキャンタージュが単なるエアレーションだけでなく、プレゼンテーションとより滑らかな飲用体験のために重要であることも強調しています。
国際基準と日本基準 ワイン用語の微妙な違いを理解する
最も顕著な違いは「ルビー (Ruby)」と「ガーネット (Garnet)」の解釈にあります。この違いは、テイスティングコメントの正確性だけでなく、国際的なワインコミュニティにおけるコミュニケーションにおいても重要な影響を及ぼします。
-
WSET基準: ワインの熟成に伴う色の進行を表現します。Purple(最も若い)→ Ruby → Garnet → Tawny(最も熟成/酸化が進んだ)という順序で色調が変化すると定義しています。WSETは、ワインの熟成度を客観的に評価するための体系的なアプローチを重視しており、色調の変化をその主要な指標の一つとしています。
-
JSA基準: 「ルビー」と「ガーネット」は、ともに「紫がかった若いワイン」の色調を表します。「ルビー」は淡い赤色を、「ガーネット」はこの若い紫がかったスペクトル内でより濃い赤色を指します。熟成したワインには「レンガ (Brick)」が使用されます。JSAのシステムは、日本のソムリエ試験や国内市場でのテイスティングコメントに特化して発展してきました。
-
JSAの新用語: 2018年には、従来の「ルビー」に相当する「ラズベリーレッド (Raspberry Red)」と、従来の「ガーネット」に相当する「ダークチェリーレッド (Dark Cherry Red)」が導入されました。これは、より具体的なイメージを喚起し、テイスター間の認識のずれを減らすことを目的とした改訂です。さらに、2022年には「オレンジ(グリ)を帯びた (Orangish (Gris))」が追加されています。これは、特に日本の甲州ワインに見られるような、ユニークな色調を表現するためのものです。
2つの異なる、広く認識されている基準(WSETは国際的、JSAは国内的)が、基本的な外観用語に対して存在するという事実は、コミュニケーションの障壁を生み出します。JSA基準で訓練されたソムリエがワインを「ガーネット」(濃く、若く、紫がかった)と表現しても、WSETで訓練されたプロフェッショナルは「ガーネット」を熟成の兆候と解釈するでしょう。この相違は、文脈(JSAかWSETか)が明確に理解されていない場合、重大な誤解につながる可能性を浮き彫りにします。例えば、日本のソムリエが「ガーネットの美しい若々しいワイン」と評したとしても、国際的なテイスターには「熟成が進んだワイン」と受け取られ、その後の風味の評価にも影響を及ぼす可能性があります。特にプロフェッショナルな環境では、ワインの外観について議論する際に、どの基準を用いているかを明示することの重要性を強調しています。また、これは文化や教育機関を超えて感覚的な言語を標準化することのより広範な課題を示唆しています。
各試験での推奨される表現と背景
JSA試験対策
-
若い赤ワインの場合、判断に迷ったら「ガーネット」と回答することが推奨されています。これは、多くの赤ワインがこの色調に該当し、安全な選択肢であるためです。
-
複数の回答が求められる場合は、基本用語と補助的用語を組み合わせて使用します(例:若いボルドーのカベルネ・ソーヴィニョンには「紫がかった、黒みを帯びた、ダークチェリーレッド」)。これにより、より詳細で正確な外観描写が可能になります。
-
濃淡については、「やや濃い」が無難な選択肢とされていますが、「明るい」や「濃い」も使用できます。
-
清澄度については、「澄んだ」が基本であり、非常に濃いワインには「深みのある」、輝きについては「輝きのある」または「落ち着いた」が用いられます。
WSETシステマティック・アプローチ・トゥ・テイスティング (SAT)
濃淡(pale, medium, deep)と色調(purple, ruby, garnet, tawny)について、構造化された記述子を提供しています。WSETのSATは、世界中で一貫したテイスティング言語を提供することを目的としており、その用語は国際的なワイン業界で広く認識されています。
特定の試験において「安全な」または「推奨される」回答が存在するという事実は、ワインテイスティングが、特に認定試験の文脈では、純粋に主観的なものではないことを示しています。特定のシステム内では、用語を適用する「正しい」方法が認識されています。これは、プロフェッショナルな目的でワインの外観用語を習得するには、感覚的属性を理解するだけでなく、制度的な慣習や、特定の評価のための語彙の戦略的適用も必要であることを意味します。
これらの違いは、各組織の歴史的発展と地域的焦点に起因します。JSAのシステムは日本の市場とソムリエ認定に合わせて調整されている一方、WSETは世界的な適用可能性を目指しています。JSAは、日本のワイン愛好家やプロフェッショナルが日本のワイン文化や食文化に合わせた表現を習得できるよう、独自の用語体系を発展させてきました。一方、WSETは、多様な国のワインを評価し、国際的なコミュニケーションを円滑にするために、より普遍的な用語の使用を推奨しています。
まとめと実践への応用
効果的なテイスティングコメント作成のポイント
-
体系的なアプローチ: 清澄度、濃淡、色調、縁の色、脚、澱といった各要素を順序立てて評価することで、すべての側面を網羅し、漏れのないコメントを作成できます。グラスを傾け、光にかざし、様々な角度から観察することで、より多くの情報を引き出すことができます。
-
正確性: 曖昧な表現ではなく、例えば「ルビー」と「ダークチェリーレッド」のように、より正確な専門用語を使用することが重要です。これにより、あなたのテイスティングコメントはより具体的で、他者にも理解しやすくなります。
-
文脈への意識: 「ルビー」や「ガーネット」などの用語を使用する際は、特定のテイスティング基準(JSAかWSETか)を意識することが不可欠です。必要に応じて、どちらの基準に基づいているかを明記することで、誤解を防ぐことができます。
-
統合: 視覚的観察を他のワインの特性(例:「濃い色はフルボディを示唆する」、「オレンジがかった縁は熟成を示す」)と関連付けてコメントすることで、より深い洞察を提供できます。外観から得られた情報を、香りや味わいの評価と結びつけることで、ワインの全体像をより立体的に捉えることができます。
-
実践: 多様なワインを定期的にテイスティングし、コメントを記述する練習を重ねることで、鋭い観察眼と正確な記述語彙を養うことができます。テイスティングノートを記録し、後で見返すことで、自身の評価の傾向や進歩を確認できます。
効果的なテイスティングコメントを作成することは、観察、分析、統合の反復的なプロセスです。それは単に用語を羅列するだけでなく、視覚的な手がかりを推測される特性(熟成度、ボディ、ブドウ品種)に結びつける一貫した物語を構築することです。JSAが基本用語と補助用語の組み合わせを強調していることは、この構造化されたアプローチを例示しています。これは、熟練したテイスターは単に色を見ているのではなく、その初期の視覚情報に基づいてワインの全体的なプロファイルに関する仮説を構築し、それを香りや味わいを通じて洗練させていくことを意味します。
日本語と英語での表現の使い分けと習得
-
バイリンガルな流暢さ: 国際的な文脈や日本特有の文脈で活動するプロフェッショナルにとって、両方の用語体系を習得することは不可欠です。例えば、海外のワイナリーを訪問したり、国際的なワインイベントに参加したりする際には、英語の用語が必須となります。
-
違いの認識: 特に「ルビー」と「ガーネット」のような用語については、誤解を避けるために、常に異なる解釈があることを認識しておく必要があります。これは、異なる文化圏のワイン愛好家やプロフェッショナルとのコミュニケーションにおいて、非常に重要なポイントです。
-
継続的な学習: JSAにおける新しい用語(ラズベリーレッド、ダークチェリーレッド、オレンジ(グリ)など)の追加は、ワイン用語が進化し続けていることを示しており、継続的な学習が求められます。ワインの世界は常に変化しており、新しいブドウ品種や醸造技術が登場するにつれて、表現方法も多様化していきます。
-
両言語での実践: 日本語と英語の両方でテイスティングとノート作成を行うことで、理解と応用力を確固たるものにすることができます。例えば、テイスティングノートを日本語と英語で併記したり、英語のワイン専門書を読んだりすることで、両方の言語での表現力を高めることができます。
グローバル化されたワイン業界において、正確なバイリンガルコミュニケーションは単なる便宜ではなく、プロフェッショナルな必須要件です。「ルビー」や「ガーネット」のような異なる用語体系から生じる誤解は、販売、教育、そして批評的な評価に影響を与える可能性があります。したがって、真の専門家は用語を知っているだけでなく、それが適用される「文脈」と「基準」を理解する必要があります。これは、多様な専門的環境での適応性と正確性を確保するために、言語的および業界固有の発展の両方への継続的な関与を必要とします。

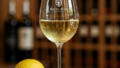
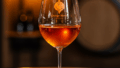
コメント