現代のファインダイニングにおいて、ワインリストは単なる飲み物の提供にとどまらず、レストランの哲学や料理との調和、そしてお客様の体験の質を決定づける非常に重要な要素となっています。その評価は、銘柄の希少性や価格だけでなく、セレクションの多様性や奥行き、情報の正確性、そしてソムリエによるサービスの品質など、多岐にわたる基準で判断されます。例えば、世界的な影響力を持つワイン専門誌「ワイン・スペクテーター」のレストラン・アワードでは、ワインリストが料理に適したセレクションであるか、幅広い愛好家に訴求するか、ヴィンテージやアペラシオン、バイ・ザ・グラスの提供、情報の正確性、そして全体的なプレゼンテーションなどが総合的に評価されます。
「日本トップクラスのワインリスト」という表現は、一様には定義できません。特定の産地やスタイルに特化した深い専門性、あるいは世界中の銘柄を網羅する広範なセレクション、さらには国際的な権威ある賞の継続的な受賞歴など、様々な側面からその価値が測られます。これは、日本のワイン市場が成熟し、多様なニーズに応える高度なワインプログラムが求められている状況を反映しています。本記事では、国際的な評価機関である「ワイン・スペクテーター レストラン・アワード」の受賞歴を持つレストランを中心に、それぞれのワインリストが持つ独自の強みとソムリエの哲学を深掘りし、「日本トップクラス」と称されるにふさわしい価値を考察していきます。
目次
日本のワインリストの進化と「日本トップクラス」の定義
日本のワイン市場は近年、目覚ましい発展を遂げ、お客様のワインに対する知識や関心も深まっています。これに伴い、レストランに求められるワインプログラムも、単なる有名銘柄の羅列から、より洗練されたキュレーションへと進化してきました。例えば、あるレストランは日本ワインの深い探求に特化し、そのテロワールの多様性や生産者の情熱を伝えることに力を入れています。また別のレストランは、カリフォルニアワインの広範なコレクションで知られ、特定の産地の奥深さを追求しています。さらに別の場所は、国際的な評価機関から継続的に表彰されており、その普遍的な質の高さが認められています。
これらの異なる強みは、「日本トップクラス」という称号が単一の基準で決まるものではなく、特定の専門性、幅広い国際性、あるいは継続的な国際的認知といった多角的な視点から評価されるべきであることを示唆しています。日本のファインダイニングシーンでは、お客様の多様な嗜好や食事の目的に応じて、最適なワイン体験を提供できるかどうかが、そのワインリストの真価を問う重要なポイントとなっています。
「日本トップクラス」のレストラン ワインリストを深掘り
ここでは、日本を代表するワインリストを持つレストランを個別に分析し、その特徴やお客様の体験に焦点を当てます。
一味真 ICHIMISHIN 日本ワインの多様性と国際的な調和
一味真は、東京都新宿区の東京オペラシティタワー53階に位置するレストランです。高層ビルから望む夜景や、昼間の青空と神宮の森の美しいコラボレーションを借景に、フレンチ、イタリアン、和食といった既存の枠にとらわれない独創的なコース料理を提供しています。総料理長は天皇皇后両陛下の行幸啓晩餐会のグランシェフを務めた長門慶次氏が務めるなど、料理界の重鎮が名を連ねています。
一味真のワインリストは、日本ワインへの強いコミットメントが際立っています。約350種類もの日本ワインを取り揃え、メニューには種類だけでなく、各都道府県別にワイナリーおよびワインの名称が記載されており、お客様が縁のある地のワインを選ぶ楽しみを提供しています。これは、日本ワインの品質と多様性の向上を背景に、その魅力を深く探求したいというお客様のニーズに応えるものです。一方で、公式ウェブサイトやお客様のレビューからは、フランス、イタリア、アメリカなど世界各国のワイン、特にシャンパーニュのセレクションも充実していることが示唆されています。ソムリエの小川貞夫氏は、フランス、イタリア、アメリカのほぼ全土を巡り、トルコ、ロンドン、そして日本ワインにも注目していると述べています。この事実は、当初の「日本ワインのみで揃えた」という表現が、日本ワインの比類ない深さを強調するものでありながら、実際には国際的なラインナップも提供していることを明確にしています。この戦略的なアプローチは、一味真が日本ワインの隆盛を牽引しつつ、同時に洗練されたお客様のために国際的なワインの最高水準を維持しようとしていることを示しています。このように、国内の優れたテロワールを深く掘り下げながら、世界の多様なワインも提供することで、日本の高級ダイニングシーンにおける「最高のワインリスト」が、地域性と国際性の両方を高いレベルで融合させる方向へと進化している様子がうかがえます。
お客様からの評価では、日本ワインの豊富さや、食事に合わせてグラスで様々な日本ワインを提案してくれるソムリエの対応が特に好評です。また、高級レストランでありながら、ワインの価格設定が「リーズナブル」であるという肯定的な意見も一部見られます。これは、提供されるワインの品質や希少性を考慮すると、お客様がその価格に高い価値を見出していることを示唆しています。高級レストランにおける「リーズナブル」という価格認識は、非常に重要な競争優位性となります。これは、一味真がプレミアムなセレクション(特に希少な日本ワインを含む)を提供しつつ、それがお客様の感覚に響く価格設定を実現していることを示しており、結果として、高額な値付けで批判を受ける競合他社と比較して、知覚価値を高めることに成功していると考えられます。
ニューヨーク グリル パーク ハイアット 東京 カリフォルニアワインの殿堂と隠れた多様性
ニューヨーク グリルは、パーク ハイアット 東京の最上階(52階)に位置し、東京の壮大なパノラマビューと共に本格的なグリル料理を提供するレストランです。映画「ロスト・イン・トランスレーション」の舞台としても世界的に知られており、その洗練された雰囲気と非日常的な空間から、記念日などの特別な日の利用に選ばれることが多い場所です。
ニューヨーク グリルのワインセラーは、国内随一のカリフォルニアワインのセレクションを誇るとされています。シャンパーニュを除けば、ほぼアメリカ産、特にカリフォルニアのワインが豊富に揃っており、カリフォルニアワインの愛好家にとっては他に類を見ない選択肢が提供されます。ヴィンテージワインのリストも充実しており、約30種類が20,000円から40,000円程度の価格帯で提供されることが報告されています。しかし、提供された詳細なワインリストの抜粋からは、意外な側面も明らかになりました。ドメーヌ・モン、平川ワイナリー、北海道ワイン、月浦ワイン、キャメルファームワイナリーなど、北海道を中心とした高品質な日本ワインも複数銘柄、比較的高い価格帯で提供されていることが確認できます。これは、当初の「ほぼアメリカ産」という記述が、彼らの主要な強みとアイデンティティを強調するものでありながら、実際にはより洗練されたキュレーション戦略を持っていることを示しています。ニューヨーク グリルは、カリフォルニアワインの強固な基盤を維持しつつ、高品質な日本ワインを取り入れることで、ワインプログラムを戦略的に多様化させています。この動きは、日本のワイン市場の成長と、多様なワインに対するお客様の関心の高まりに応えるものです。特定のニッチに特化しながらも、市場のトレンドに適応し、高品質な国内ワインを取り入れることで、より幅広いワイン愛好家にアピールし、トップティアの地位を維持していると考えられます。
お客様からは、ホテルの最上階からの眺望、活気がありながらも落ち着いた雰囲気、そして生演奏を聴きながらの優雅な食事体験が高く評価されています。ビュッフェ形式の前菜は種類こそ多くないものの、質が高く、自家製ベイクドリコッタチーズのような記憶に残る一品もあると評されています。アレルギー対応もしっかりしており、安心して食事ができるという声もあります。一方で、価格に関しては、「高すぎる」「この値段の価値はない」という意見も一部見られます。ランチとワイン1杯で2名で25,000円を超える会計になることもあり、そのコストパフォーマンスに疑問を呈する声もあります。しかし、多くの顧客は、雰囲気、味、接客を総合的に考慮すると「十分に行く価値がある」と感じており、特別な日や記念日の利用には最適であると認識されています。この価格に対する評価の二極化は、ニューヨーク グリルが提供する「総合的なラグジュアリー体験」が、一部のお客様にとっては価格を上回る価値を提供している一方で、純粋な料理やワインの価格対効果を重視するお客様にとっては高く感じられる可能性があることを示しています。つまり、ブランド力と非日常的な空間が、ワインリストの魅力と相まって、お客様の知覚価値を大きく左右する要因となっていることがうかがえます。
est フォーシーズンズホテル東京大手町 革新的なフレンチと国内外ワインの融合
estは、フォーシーズンズホテル東京大手町の39階に位置するコンテンポラリーフレンチレストランです。日本の旬の食材を積極的に取り入れ、革新的なフレンチを提供しています。2023年にはアメリカの「ワイン・スペクテーター」誌による「ベスト・オブ・アワード・オブ・エクセレンス」を受賞しており、そのワインリストの質の高さが国際的に認められています。
estのワインリストは、国際的な評価機関から高い評価を受けています。2023年の「ワイン・スペクテーター レストラン・アワード」で「ベスト・オブ・アワード・オブ・エクセレンス」を受賞したことは、そのセレクションが優れた広がりと深さ、そして質の高いプレゼンテーションを備えていることを示しています。ワインリストは、様々な日本のワイナリーや酒蔵からのセレクションに加え、ヨーロッパのヴィンテージワインや新世界のワインも幅広く取り揃えています。ワインペアリングのオプションも充実しており、「グラン・ヴァン」(70,000円)、「厳選フレンチワイン」(30,000円)、「国内ワインと日本酒」(25,000円)といったコースが提供されています。これは、お客様の予算や好みに応じて、多様な選択肢を提供していることを示しています。estのワインリストは、国際的な基準に準拠した卓越したワインプログラムを提供しつつ、日本の豊かなテロワールから生まれるワインや日本酒にも深く焦点を当てています。このアプローチは、グローバルな視点とローカルな要素を融合させることで、世界のワインシーンにおける日本の存在感を高め、同時に国内のワイン愛好家にも新たな発見を提供しています。
estのワインサービスは、シェフソムリエの志村武士氏が統括しており、彼を筆頭に合計3名のソムリエがワイン選びを担当しています。志村氏は20年のソムリエ経験を持ち、ミッシェル・トロワグロ出身であるとされています。彼の哲学は、お客様にワインをより深く理解してもらうこと、そしてソムリエになりたい人を増やすという使命感に基づいています。彼は「ソムリエはこうあるべき」という固定観念にとらわれず、常に新しいアプローチを模索し、お客様の五感に響く体験を提供することを目指しています。志村氏の顧客中心の哲学は、ワインリストのキュレーションとサービスの両方に反映されています。彼は、単に高価なワインを提供するだけでなく、それぞれの料理に最適なペアリングを提案し、ワインの物語や背景をお客様に伝えることに重点を置いています。
お客様からは、ソムリエによるシャンパンやワインの丁寧な説明、個室での快適な食事体験、そしてコース料理とワインペアリングの質の高さが好評を得ています。特に、デザートの独創性や、日本酒とのペアリングの相性の良さも評価されています。一方で、価格に関しては、「ホテルでのアルコールとはそういうものだと頭では理解しているものの、やはりひきつけを起こしてしまいそうなほど高い」という意見や、ノンアルコールペアリングの価格設定に対する不満も一部見られます。また、料理の見た目の美しさや味は評価されるものの、「ワクワク感、次何が来るのかと行った高揚感」や「ゴージャス感」が不足していると感じるお客様もいるようです。これは、高級レストランにおいては、単に品質が高いだけでなく、お客様の期待を超えるような感動やサプライズを提供することの重要性を示唆しています。
華暦 ザ カハラ ホテル&リゾート横浜 和食とワインの新たな提案
華暦は、ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜に位置する日本料理レストランです。世界的な影響力を持つワイン専門誌「ワイン・スペクテーター」のレストラン・アワード2024において、昨年に引き続き2年連続で「ベスト・オブ・アワード・オブ・エクセレンス」に選出されており、そのワインリストの卓越性が国際的に認められています。
華暦が受賞した「ベスト・オブ・アワード・オブ・エクセレンス」は、「ワイン・スペクテーター」誌が定める3段階の賞のうち、2番目に高い評価です。この賞は、複数のワイン生産地域にわたる優れた広がり、トップ生産者のヴィンテージの深い垂直方向の深さ、そして優れたプレゼンテーションを持つワインリストに授与されます。通常、350種類以上のセレクションを提供し、真剣なワイン愛好家にとっての目的地となるような、ワインへの深いコミットメントを示すレストランが対象となります。華暦のワインリストは、iPadで提供され、フランスのクラシックな銘柄から「第三世界」のワイン、そして日本ワインまで、幅広いラインナップを誇ります。これにより、ワイン愛好家にとっては選びがいのある充実したリストとなっています。特に注目すべきは、DRC(ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ)のような極めて希少で高価なワインの飲み比べが提供されるイベントがあることです。これは、華暦が単に幅広いセレクションを提供するだけでなく、真に特別な体験を求めるお客様のために、最高峰のワインも用意していることを示しています。ワインはグラスで2,530円から、ボトルで10,120円から提供されています。和食という伝統的な料理に、これほど多様で質の高い国際的なワインリストを調和させている点は、華暦のワインプログラムの大きな強みです。これは、和食とワインのペアリングの可能性を最大限に引き出し、お客様に新たな食体験を提供しようとするレストランの意図を示しています。
華暦では、ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜のソムリエに加え、グランメゾン「アピシウス」のエグゼクティブソムリエ情野博之氏を招聘したコラボレーションディナーを開催するなど、外部の著名なソムリエとの連携も積極的に行っています。これにより、複数のエグゼクティブソムリエが厳選したワインやシャンパーニュが提供され、お客様は至高のひとときを過ごすことができます。お客様のレビューでも、ソムリエが厳選した日本酒の利き酒セットが料理と合わせて美味しく、満足度が高かったという声が寄せられています。和食という繊細な料理にワインを合わせるには、深い専門知識と経験が必要です。複数のソムリエが協力し、国内外の多様なワインをキュレーションすることで、華暦は和食とワインの新たな調和を追求し、お客様に最高のペアリング体験を提供していると考えられます。
ソムリエの哲学が織りなすワイン体験の深化
真に優れたワインリストは、単なる銘柄の羅列ではありません。そこには、ソムリエの深い知識、経験、そしてお客様への情熱が息づいています。例えば、一味真のワインリストは、1995年に世界最優秀ソムリエコンクールで優勝し、日本ソムリエ協会の会長も務める田崎真也氏が監修しています。彼の世界的な知見と権威は、リスト全体の信頼性と魅力を大きく高めています。常駐ソムリエの小川貞夫氏は、フランスの「美食会メートルコンセイエ」受賞歴を持つなど、ワイン、シャンパーニュ、カクテル、チーズ、日本酒、紅茶など多岐にわたる専門知識とタイトルを保持しています。小川氏の哲学は、世界中のワイナリーや蒸留所を自ら訪問し、造り手の哲学と情熱が伝わる「魂のこもった」ワインをセレクトすることにあります。この体制は、ワインプログラムにおいて非常に強力なモデルを構築しています。田崎氏の関与は、リストが普遍的な卓越性を保証する「お墨付き」となり、幅広い層にアピールする要素となります。一方、小川氏の深い個人的な関わりとキュレーションは、各ボトルに独自の個性と魅力的な物語を吹き込みます。これにより、単なる銘柄の羅列ではなく、それぞれのワインが持つ背景や生産者の情熱をお客様に伝えることが可能になります。
また、estのワインサービスを統括するシェフソムリエの志村武士氏の哲学は、お客様にワインをより深く理解してもらうこと、そしてソムリエになりたい人を増やすという使命感に基づいています。彼は「ソムリエはこうあるべき」という固定観念にとらわれず、常に新しいアプローチを模索し、お客様の五感に響く体験を提供することを目指しています。志村氏の顧客中心の哲学は、ワインリストのキュレーションとサービスの両方に反映されています。彼は、単に高価なワインを提供するだけでなく、それぞれの料理に最適なペアリングを提案し、ワインの物語や背景をお客様に伝えることに重点を置いています。このアプローチは、お客様がワインを単なる飲み物としてではなく、食事体験の一部として深く味わうことを可能にします。ソムリエの専門知識と情熱が、ワインリストの魅力を最大限に引き出し、お客様の体験の質を向上させる上で不可欠な要素であることが示されています。
多様なワイン提供の形 泊まれるワイナリーという新提案
従来のレストランでのワインリストの概念を超え、ワインをより深く体験できる「泊まれるワイナリー」という新しいアプローチも注目されています。これは、単にワインを飲むだけでなく、その生産地を訪れ、醸造過程を学び、生産者の哲学に触れることで、ワインへの理解と愛着を深める体験を提供します。お客様は、ブドウ畑の広がる風景の中で、土壌の特性や気候がワインの風味にどう影響するかを肌で感じることができます。また、醸造所の見学では、発酵や熟成の過程を間近に見ることで、ワインがどのようにして造られるのかを具体的に知ることができます。
具体的な例としては、以下のような施設が挙げられます。
-
カーブドッチワイナリー&カーブドッチヴィネスパ (新潟県新潟市): 「新潟のナパ」と称されるこの地で、自家栽培・自家製ワインと露天温泉を楽しむことができます。ここでは、ワインと温泉というユニークな組み合わせで、心身ともにリラックスしながらワイン文化に浸ることができます。
-
ヴィラデスト ガーデンファームアンドワイナリー (長野県東御市): 自家農園で栽培されたブドウから作られるワインを、美しいガーデンと共に味わえる施設です。四季折々の自然の中で、ワインが育まれる環境を直接体験し、その土地ならではの味わいを感じることができます。
-
まるき葡萄酒&笛吹川温泉 別邸 坐忘 (山梨県甲州市): 日本最古のワイナリーの一つである「まるき葡萄酒」でワインを堪能し、近隣の温泉宿でくつろぐことができます。歴史あるワイナリーの伝統に触れながら、日本のワイン造りの奥深さを学ぶことができます。
これらの「泊まれるワイナリー」は、ワインリストが提供する情報や選択肢を、実際の生産現場での五感を通じた体験へと拡張するものです。このアプローチは、ワインの背景にある物語や文化に触れることで、お客様のワインに対する関心を一層深め、よりパーソナルな繋がりを築くことを可能にします。これは、ワインリストの価値が、単なる品揃えの豊富さだけでなく、ワインを取り巻く体験全体へと広がっていく未来の方向性を示唆しています。
ワインリストを評価する基準とは
日本におけるワインリストの評価は、国際的な基準だけでなく、国内独自の評価システムによっても行われています。これにより、日本のワイン文化の多様性と発展が促進されています。
ワイン・スペクテーター レストラン・アワードの評価基準
「ワイン・スペクテーター レストラン・アワード」は、世界的に権威のある評価基準です。その評価は、ワインのエキスパートである審査員によって多角的に行われます。主な評価項目は以下の通りです。
-
ワインセレクションの質と多様性: 興味深いセレクションであるか、料理との相性が適切か、幅広い愛好家にアピールするか。単に高価なワインを揃えるだけでなく、様々な価格帯やスタイルのワインをバランス良く配置し、お客様の多様なニーズに応える柔軟性が求められます。
-
リストの規模と奥行き: 提供されるワインの銘柄数(アワード・オブ・エクセレンスは90種類以上、ベスト・オブ・アワード・オブ・エクセレンスは350種類以上、グラン・アワードは1000種類以上)が重視されます。また、複数のワイン生産地域にわたる広がりや、トップ生産者のヴィンテージの深さも評価の対象となります。これにより、お客様は幅広い選択肢から、自身の好みに合ったワインを見つけることができます。
-
情報の正確性: ヴィンテージ、アペラシオン、生産者名、スペルなどが正確に記載されているか。リストの情報が正確であることは、お客様が安心してワインを選び、ソムリエとの信頼関係を築く上で不可欠です。
-
プレゼンテーション: リスト全体の構成や見やすさ。iPadでの提供や、産地ごとの分類など、お客様が快適にワインを選べるような工夫が評価されます。
-
価格設定: 価格自体は評価基準ではないものの、リストの価格帯(安価、中程度、高価)が考慮されます。お客様が提供される価値に対して、価格が適切であると感じるかどうかが重要です。
-
総合的なサービス: ワインの保管状態、サービス品質、ペアリングの提案能力。ソムリエの知識やお客様への対応、ワインの提供温度やグラスの状態など、細部にわたるサービス品質が、ワイン体験全体の満足度を左右します。
この賞は、「アワード・オブ・エクセレンス」「ベスト・オブ・アワード・オブ・エクセレンス」「グラン・アワード」の3段階で構成され、上位の賞ほど、より広範で深いセレクションと、ワインプログラムへの強いコミットメントが求められます。
日本ワイナリーアワードの評価基準
日本独自の評価基準としては、「日本ワイナリーアワード」があります。これは、日本のワイナリーの品質を評価し、表彰するものです。審査は地方区および全国区の審査員によって行われ、以下の基準で評価されます。
-
品質の一貫性: 赤や白などスタイル別で品質にばらつきがないか。特定のヴィンテージだけでなく、継続的に高品質なワインを生産しているかが重視されます。
-
安定性: 収穫年に左右されず品質の安定感があるか。天候に左右されやすいブドウ栽培において、毎年安定した品質のワインを造り続ける技術と努力が評価されます。
-
コストパフォーマンス: 価格に対して優れた価値を提供しているか。高価なワインだけでなく、手頃な価格帯でも高品質なワインを提供できるワイナリーが評価されます。
-
バランスと高貴さ: 複雑性、凝縮感などのバランスに優れ、高貴さを持っているか。ワインの構成要素が調和し、飲み手に深い感動を与えるようなワインが求められます。
-
テロワールの表現: 産地の特性をワインが表現できているか。その土地ならではの気候、土壌、品種の個性がワインに反映されているかが重要な評価ポイントです。
-
個性: ワインが一貫して個性を持っているか。他のワインとは一線を画す独自のスタイルや哲学が、ワインに表現されているかが評価されます。
最高位は「5つ星」で、「多くの銘柄・ヴィンテージにおいて傑出した品質のワインを生み出すワイナリー」が選ばれます。2025年には、審査対象374ワイナリーのうち281ワイナリーが表彰されており、日本のワイン生産の質の向上が示されています。これらの異なる評価基準は、ワインリストの「最高」が多面的な概念であることを明確に示しています。国際的な賞は、広範なセレクションとグローバルな視点での品質を重視する一方で、国内のアワードは、日本固有のテロワール表現やワイナリーの個性に焦点を当てています。これにより、日本のワインリストは、国際的な水準を満たしつつ、国内の多様なワイン文化を深く掘り下げるという、独自の進化を遂げていることがわかります。
まとめ:日本におけるワインリストの輝かしい未来
「日本トップクラスのワインリスト」を巡る探求は、単一の明確な答えが存在しない、多角的で複雑なテーマであることが明らかになりました。本記事で分析した主要なレストランは、それぞれ異なる強みと哲学を持ち、多様な側面から「最高」のワインリストを定義しています。
これらの分析から、日本における「最高のワインリスト」は、以下の要素を高い次元で融合させたものであると結論付けられます。
-
多様性と専門性の両立: 特定の産地やスタイルに深い専門性を持ちつつ、国際的な銘柄や新たなトレンド(特に日本ワイン)も柔軟に取り入れることで、幅広いお客様のニーズに応える能力が求められます。これは、お客様が求めるものが多様化する現代において、レストランが競争力を維持し、新たな顧客層を獲得するために不可欠な要素です。
-
ソムリエの役割の深化: ワインの選定だけでなく、お客様との対話を通じてその好みや料理との相性を引き出し、ワインの物語を伝えることで、単なるサービスを超えたパーソナルな体験を提供することが不可欠です。ソムリエは、お客様にとってワインの世界への案内人であり、その知識、情熱、そしてコミュニケーション能力が、ワインリストの真の価値を引き出す鍵となります。
-
知覚価値の最大化: 高級なワインリストにおいては、価格設定とお客様が感じる価値とのバランスが極めて重要です。単に高価であるだけでなく、非日常的な空間、卓越したサービス、そして記憶に残る体験が、価格を上回る価値を提供することで、お客様の満足度とロイヤルティを築き上げます。お客様が「この価格を払う価値がある」と感じるような、総合的な体験の提供が求められます。
-
体験としてのワイン提供: ワインリストは、単なる飲み物の選択肢ではなく、食事体験全体の一部として、あるいは「泊まれるワイナリー」のように、より没入感のある体験として提供されることで、お客様のワインに対する関心を一層深め、新たな市場を創造する可能性を秘めています。ワインの背景にあるストーリーや文化を伝えることで、お客様はより深くワインと繋がり、その価値を再認識することができます。
日本のワインリストは、国際的な評価基準に挑戦しつつ、独自の文化や食材との調和を追求することで、世界でも類を見ない進化を遂げています。今後も、これらの要素が複合的に作用し、日本のワインシーンはさらなる高みへと発展していくことが期待されます。

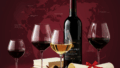
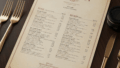
コメント