近年、日本の酒類市場において、まさに驚異的な成長を遂げているのが「国産クラフトジン」です。その生産量は過去5年間で約3.9倍という目覚ましい拡大を見せ、2023年には国内出荷量が前年比113.4%を記録するなど、その勢いはとどまることを知りません。この急速な成長の背景には、日本の豊かな自然が育む多様でユニークなボタニカルの活用、そして長年にわたり培われてきた日本独自の伝統的な酒造技術と、現代の革新的な蒸留技術が融合した結果が深く根ざしています。国産クラフトジンは、単なる飲料の枠を超え、日本の風土、文化、そして職人の情熱を凝縮した「液体の工芸品」として、国内外から熱い注目を集めているのです。
目次
国産クラフトジンとは何か その定義と魅力の深掘り
クラフトジンには、実は明確な法的定義が存在しません。一見すると市場の混乱を招きかねない要素に見えるかもしれませんが、この定義の柔軟性こそが、作り手に対してベーススピリッツの選択、ボタニカルの組み合わせ、蒸留方法などにおいて極めて高い自由度を与えています。この自由な発想が、各地域の気候風土を反映したユニークなボタニカルの使用や、日本の伝統的な酒造技術と現代の蒸留技術の革新的な融合を促進し、結果として「個性豊かな香りと味わい」を持つ、世界に類を見ない多様な国産クラフトジンが市場に次々と生まれる原動力となっています。したがって、定義の欠如は、日本のクラフトジン市場において、イノベーションと地域性の表現を促すポジティブな要因として機能しており、これが急速な市場拡大の一因となっています。
一般的に、クラフトジンとは、職人の技術と、その土地や地域の伝統が深く込められた個性的なジンを指します。大手飲料メーカーによる大量生産品とは異なり、小規模な蒸留所や、日本酒、焼酎、ビールメーカーといった異業種からの新規参入によって、少量ながらもこだわり抜かれた製品が生まれる傾向が強いのが特徴です。ジンの風味付けに必須とされるジュニパーベリーに加え、国産クラフトジンでは通常4〜10種程度のボタニカルが使用されますが、そのレシピは各銘柄で大きく異なります。日本の酒税法ではジンが「スピリッツ」に分類され、エキス分が2度未満の酒類と定義されますが、ベーススピリッツやボタニカルの種類に関する具体的な法的規定は存在しません。これは、EU法におけるアルコール度数や着色料に関する規定とは対照的であり、日本のクラフトジンにさらなる自由度を与えています。作り手の情熱、試行錯誤、そして素材選びから製造方法、ボトルデザインに至るまでの強いこだわりが、クラフトジンの品質と個性を形成する重要な要素となっています。
「クラフト」という言葉が示すように、国産クラフトジンは単なる工業製品ではなく、作り手の技術と熱い想いが強く込められた「工芸品」としての側面を持ち合わせています。小規模生産ならではの丁寧な手仕事は、風味の繊細さと品質の高さを実現し、素材へのこだわり、独自の製法開発、地元農家との連携といった製品が持つ物語性が必然的に生まれます。この物語は、製品に深みと人間味を与え、単なるアルコール飲料としてだけでなく、日本の多様な魅力を伝える文化的な存在としての価値を高めています。現代の消費者は、製品の機能的価値だけでなく、その背後にある物語や作り手の情熱、そして製品が持つ文化的な意味合いに価値を見出しているため、この傾向は、クラフトジンのプレミアム化や、消費者との感情的な繋がりを強化する上で重要な要素となっています。
日本産クラフトジンの唯一無二の独自性
日本産クラフトジンの最大の魅力は、伝統的なジュニパーベリーに加え、各地域の気候風土を反映したユニークなボタニカルが、それぞれのジンに個性的な香りと味わいを添えている点にあります。例えば、北海道ではハスカップやアカエゾマツ、京都では緑茶や玉露、広島ではレモン、和歌山では紀州のスギやヒノキ、沖縄ではシークヮーサーやグァバなど、地域独自の素材が選ばれています。これらのボタニカルは、単なる香り付けに留まらず、日本の四季折々の風景や、人々の暮らしを映し出す鏡のような役割を果たしています。積丹半島では、自生するビャクシン(ジュニパーベリー)やハマナス、ローズなどが活用され、その土地ならではの風味を生み出している事例もあります。
日本の地理的・気候的多様性は、各地域に固有の豊かな植物資源(ボタニカル)をもたらしています。これらの地域固有の素材を積極的に活用することは、他国のジンにはない「和の要素」や「日本の四季折々の風景や文化を彷彿とさせる」独自の風味プロファイルを確立します。この独自性が、国際市場において「日本文化を反映した調和の良さ」として高く評価され、海外での需要拡大の大きな要因となっています。地域固有の資源を最大限に活用する戦略は、製品の独自性を高めるだけでなく、グローバル市場での競争優位性を確立する上で極めて効果的であると評価できます。これは、地方創生と国際ビジネスの成功を両立させるモデルとなりうるでしょう。
日本酒や焼酎など、日本の伝統的な酒造りの技法と現代の蒸留技術を融合させることで、深みのあるコクやまろやかな口当たりを実現し、世界でも評価される高い品質を確立しています。日本酒や焼酎の蔵元がクラフトジン市場に参入する動きは、長年培ってきた日本の伝統的な醸造・蒸留技術をジン製造に応用する機会を生み出しました。これに最先端の蒸留技術や各蒸留所独自の製法を組み合わせることで、複雑でありながら調和の取れた洗練された味わいを実現しています。この品質の高さが、国際的な酒類コンペティションでの多数の受賞や世界的な評価に直接的に繋がっています。既存の産業(伝統酒造)の強み(技術、知見)を新しい分野(クラフトジン)に応用し、さらに革新的なアプローチを加えることで、短期間で世界レベルの品質を達成できることを示しています。これは、異業種からの新規参入を促す成功モデルとしても注目されます。さらに、地元農家との連携による高品質な素材の安定調達や、廃棄される果物・野菜をボタニカルとして使用する取り組みが広がり、地域活性化や持続可能性への貢献も注目されています。
市場の変遷と驚異的な成長の背景
日本におけるジンの歴史は古く、サントリーが1936年に「ヘルメスドライジン」を発売し、戦後、バーを中心にカクテルとして楽しまれてきました。しかし、現代のクラフトジンブームは、2000年代以降にイギリスで起こったクラフトジンブームが日本に伝播したことに端を発します。日本国内でのクラフト酒類ブームの始まりは、1994年の酒税法改正による小規模ビール醸造会社の登場と「地ビール」の誕生に遡ります。この酒税法改正は、小規模な酒類製造免許の取得を可能にし、それまで大手企業に独占されていた酒類製造の門戸を広げました。これにより、全国各地で個性豊かな地ビールが誕生し、消費者の間で「こだわり」や「多様性」を求める需要が喚起されました。その後の「クラフトビール」ブームは、消費者側で高品質な小規模生産品への関心を高め、同時に生産者側にも小規模ながら高品質な製品を製造・販売するビジネスモデルの可能性を示しました。この先行するクラフト酒類ブームが形成した市場の土壌の上に、日本酒やウイスキーも「クラフト化」の波が押し寄せ、ジンにおいては、日本酒や焼酎の蔵元が市場に参入し始めました。
そして、2016年に京都で日本初のジン専門蒸留所「京都蒸溜所」が誕生したことが、国産クラフトジンブームの本格的な火付け役となりました。世界的なウイスキーブームは、新規蒸留所の開設ラッシュを引き起こしましたが、ウイスキーは数年にわたる樽熟成が必要であり、販売開始までのリードタイムが長く、多大な初期投資(樽、熟成庫)を要します。これに対し、ジンは熟成が不要で、比較的短期間かつ少ない資本で製造・販売が可能であるという特性があります。この特性から、多くの新規ウイスキー蒸留所が、ウイスキーが熟成するまでの間のキャッシュフローを確保する戦略として、ジン製造に参入しました。このように、ウイスキー市場の活況が、直接的ではないものの、クラフトジン市場の供給側の多様性と規模を間接的に加速させたという、興味深い産業連鎖が見られます。これは、隣接する市場の動向が、予期せぬ形で新たな市場形成を促進する好例であると言えます。2020年にはサントリーが「翠」を発売し、市場は一気に1.5倍に拡大しました。これは日常の食卓で気軽に楽しめる「ジンソーダ」スタイルの飲用機会の拡大にも貢献し、ジンをバーの専門的な飲み物から一般家庭の食卓へと飲用シーンを広げ、新たな顧客層(特にカジュアル層)の獲得に成功しています。
主要な国産クラフトジンブランドとその特徴
日本のクラフトジン市場には、多様なブランドが存在し、それぞれが独自の物語と風味を提供しています。
-
京都蒸溜所「季の美 京都ドライジン」
2016年に日本初のジン専門蒸留所として京都で誕生し、国産クラフトジンブームの火付け役となりました。お米由来のスピリッツをベースに、柚子、緑茶、山椒など和素材を含む11種類のボタニカルを使用し、京都伏見の伏流水でブレンドされています。特筆すべきは、ボタニカルをその特性に応じて6つの「エレメント」(ベース、シトラス、ティー、スパイス、フローラル、ハーバル)に分け、それぞれ個性を引き出す独自の製造方法を採用している点です。これにより、複雑でありながら調和の取れた繊細な風味を表現しています。その品質は国際的にも高く評価され、IWSC(インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション)で最高賞を受賞し、日本のジン市場のプレミアムカテゴリーで売上第1位を獲得しています。
-
サントリー「ジャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉」
サントリーが手がける「ROKU」は、日本の四季を象徴する6種類の和素材(桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子)を豊富に取り入れた、華やかな香りと複層的な風味が特徴です。ジュニパーベリーを中心としたオーソドックスなジン原酒と、6つの和素材を使ったボタニカル原酒をブレンドして完成させます。この繊細なバランスと「日本文化を反映した調和の良さ」は、ロンドンのバーテンダーからも高く評価され、世界中で楽しまれています。2019年には世界トップ5のジンに選出されるなど、その品質は国際的に認められています。
-
桜尾蒸留所「SAKURAO GIN」
2018年に広島県の中国醸造が設立した比較的新しいブランドで、広島から世界に羽ばたくジンとして注目されています。クリアなテイストのベーススピリッツにボタニカルを浸漬して蒸留するスティーピング方式と、蒸留経路に金属製のバスケットを設けて蒸気で香味を抽出するヴェイパー方式を同時に行うハイブリッド方式を採用し、各ボタニカルに最適な方法で香味を抽出している点が特徴です。この製法により、複雑で奥行きのある味わいを実現し、国際的な酒類品評会で多数の賞を受賞しています。
-
紅櫻蒸溜所「9148」
北海道初のクラフトジン蒸留所として2018年に設立されました。ジョージ・オーウェルの小説「1984」にちなんで名付けられ、自由な社会への希望を込めたブランドです。北海道の地下水と、昆布、干し椎茸、切り干し大根といった珍しい北海道名産品を含む多様なボタニカルを使用しています。定番の「9148 0101」は、日高昆布のうまみとジュニパーベリーの爽やかな甘みが特徴の「UMAMIジン」として知られ、和食とのペアリングも提案されています。季節限定ボトルも定期的にリリースしており、地域の旬の素材を活かした多様なフレーバーを提供しています。
-
越後薬草「80 “YASO” GIN」
新潟県の越後薬草が手がける「YASO」は、野草酵素の研究を40年以上重ねてきた同社の知見と技術が結集したブランドです。健康食品製造の発酵過程で発生するアルコールを有効活用し、廃棄物ゼロを目指すSDGsを念頭に置いた循環型製造を行っている点が大きな特徴です。よもぎなどの野草を軸に80種の素材からなる「80 “YASO” SPIRITS」をベースに、ジュニパーベリーやジンセンベリーなど23種のボタニカルを加え、香り付けしています。環境に配慮した製造プロセスは、現代の倫理的消費意識の高い層に強く訴求しています。
-
NUMBER EIGHT DISTILLERY「NUMBER EIGHT GIN」
横浜みなとみらいの商業施設内にある都市型蒸留所「NUMBER EIGHT DISTILLERY」で造られています。蒸留所名にちなんで8種類のボタニカルを使用しており、ベーススピリッツには日本酒蔵の吟醸酒粕焼酎を採用しています。ボタニカルにはジュニパーベリーのほか、HUGEグループのレストランで常時使用しているイエルバブエナ(キューバンミント)、レモンバーベナ、地元神奈川県産の神奈川みかん、無農薬レモン、そして併設するブリュワリーとロースタリーから生ホップ、コーヒー豆、さらにメキシカンレストランで大量に消費されるアボカドの廃棄される種といったユニークな素材が使われています。特にアボカドの種活用は、フードロス削減への貢献という点で、環境意識の高い消費者層にもアピールしています。華やかさと力強さを併せ持ち、東京ウイスキー&スピリッツコンペティションで銀賞を受賞するなど、その品質も高く評価されています。
-
まさひろ酒造「まさひろオキナワジン」
沖縄県で泡盛を製造するまさひろ酒造が、2017年に沖縄初のクラフトジンとして販売を開始しました。泡盛をベーススピリッツに、シークヮーサー、グァバ(葉)、ゴーヤー、ローゼル(ハイビスカス属)、ピィパーズ(ヒハツモドキ)など、沖縄らしい6種類のボタニカルを使用しています。長年の泡盛製造で培った単式蒸留機を2種類用いた独自の「ハイブリッド製法」が特徴で、シークヮーサーのフレッシュで爽やかな香りと、南国を感じさせるスパイシーさやビター感が楽しめます。沖縄の風土を色濃く反映した、唯一無二の味わいが魅力です。
-
那覇晴蒸溜所「那覇晴GIN」
沖縄県那覇市に設立された那覇晴蒸溜所が手がけるクラフトジンです。厳選した沖縄のボタニカルを贅沢に使用しており、ベースとなるジュニパーベリーの風味を生かしながら、名護の勝山シークヮーサーを中心に、南国の柑橘類の爽やかな香味を表現しています。その他、宜野座村の純黒糖や南城市のピィパーズ(島胡椒)、さんぴん茶、月桃などもボタニカルとして使用され、沖縄の大地と太陽の恵みを感じさせる風味豊かなジンに仕上がっています。炭酸やトニックウォーターで割ると、さらに香り高く楽しむことができます。
世界が認める品質 国際的な評価と受賞歴
日本産クラフトジンは、その品質の高さと独自性により、国際的な酒類品評会で数々の賞を受賞し、世界中で高い評価を得ています。これは単なる名誉に留まらず、海外市場での需要を牽引し、輸出量の大幅な増加に直結しています。
-
**京都蒸溜所「季の美 京都ドライジン」**は、IWSC(インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション)で「Trophy」「Gold – Outstanding」を受賞し、日本のジン生産者として初めて「インターナショナル ジン プロデューサー オブ ザ イヤー」を2度受賞する快挙を成し遂げています。この受賞は、日本のクラフトジンが世界最高峰の品質基準を満たしていることの明確な証拠であり、国際的なブランド認知度を飛躍的に高めました。
-
**サントリー「ジャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉」**は、2019年には世界トップ5のジンに選出されるなど、国際的な評価を獲得しています。その洗練された和の風味は、海外のバーテンダーや愛好家からも絶賛され、日本のクラフトジンの代表格として広く認知されています。
-
**ニセコ蒸溜所「ohoro GIN(スタンダード)」**は、2024年2月にはイギリス・ロンドンで開催された「World Gin Awards 2024」のクラシックジン部門において、日本産ジンとして初めて部門別最高賞となる「World’s Best」を受賞しました。これは、世界中のジンの中から最も優れた一本として選ばれたことを意味し、日本のクラフトジンの品質が世界でトップレベルにあることを決定づける快挙と言えるでしょう。
-
その他にも、桜尾蒸留所「SAKURAO GIN」、越後薬草「80 “YASO” GIN」、Alembic大野蒸留所「Alembic Dry Gin HACHIBAN」、本坊酒造「Japanese GIN 和美人」など、多くの国産クラフトジンが国際的な品評会で最高金賞や金賞を受賞しています。これらの受賞は、日本産クラフトジンが国際的な舞台でその品質と独自性を高く評価されていることを客観的に証明しています。特に、柚子や山椒、緑茶、桜など、日本の風土で育まれたボタニカルをふんだんに使用することで、個性的で深みのある味わいを生み出している点が海外で高く評価されており、輸出量の増加にも繋がっています。これらの国際的な評価は、日本のクラフトジンが単なるトレンドではなく、確固たる品質と独自性を持つカテゴリーとして世界市場に定着しつつあることを示唆しています。
消費者トレンドと購入体験
クラフトジン市場の拡大は、消費者の行動や嗜好の変化に深く関連しています。現代の消費者は、単に安価な製品を大量に消費するのではなく、**量よりも質を重視する「プレミアム志向」**を強めています。彼らは、高品質で職人技が光る飲料に対して強い関心を示し、ユニークで本物の体験を求めています。プレミアム・ジンやクラフト・ジンは、高品質の原料、特徴的なボタニカル、革新的な製造技術を使用していることが特徴であり、優れた製品には対価を支払うことを厭わない目の肥えた消費者に強く訴求しています。2020年にはプレミアム・ジン・セグメントが世界のジン売上のほぼ40%を占めるなど、この傾向は顕著であり、今後もこの流れは加速すると考えられます。
製品の背景にあるストーリー性への強い関心も市場を牽引する重要な要素です。多くのクラフトジンには、造り手の熱い想いや、素材へのこだわり、地域との連携といった物語が込められています。例えば、各地の厳選されたボタニカルを用いることでその土地の風土と文化を表現したり、地元農家と連携して高品質な素材を安定的に調達したりする取り組みは、単なる味わいだけでなく、その背景にあるストーリーが世界的な評価を受け、日本らしさを伝える文化的な存在へと成長しています。消費者は、ブランドの背景にあるストーリーやクラフトマンシップに価値を見出しており、これが製品への愛着や購入意欲を高めています。この「物語消費」の傾向は、特に若年層を中心に顕著であり、SNSなどを通じて製品のストーリーが共有されることで、さらなる拡散と共感を呼んでいます。
また、ジンの飲用機会が多様化しています。かつてはバーでカクテルとして楽しまれることが多かったジンですが、近年では日常の食卓でも気軽に楽しめる「ジンソーダ」スタイルでの飲用が増加しています。特に、国産の和素材にこだわり、ソーダ割りでも手軽に楽しめるジンの登場がこのトレンドを後押ししました。これにより、ジンは「バーで楽しむお酒」という専門的なイメージから、食事中などどんなシーンでも楽しめる身近なお酒になりつつあります。このカジュアル化は、新たな顧客層の獲得に繋がり、市場全体の拡大に大きく貢献しています。
さらに、持続可能性(SDGs)への貢献も消費者の選択に影響を与えています。地元農家と協力し、廃棄される果物や野菜をボタニカルとして使用する取り組みや、製造過程で発生する副産物を有効活用し、廃棄物ゼロを目指す循環型製造など、環境や地域社会に配慮したクラフトジンが増えています。このような取り組みは、消費者の倫理的消費意識に合致し、製品の魅力を一層高めています。消費者は、単に美味しいだけでなく、社会や環境に良い影響を与える製品を選ぶ傾向が強まっており、クラフトジンのサステナブルな取り組みは、ブランドの信頼性と魅力を高める重要な要素となっています。
国産クラフトジンは、多様なチャネルを通じて消費者に届けられています。オンラインストアは、クラフトジンの購入において重要な役割を果たしており、信濃屋の公式通販サイトや高島屋のクラフトジン特集、各蒸留所の公式オンラインショップなど、多くの酒販店や蒸留所がオンライン販売を展開しています。これにより、消費者は全国各地の多様なクラフトジンを自宅から手軽に購入できるようになり、流通の自由度が高まっています。実店舗では、専門性の高い酒販店がクラフトジンの魅力を伝えています。GLOBAL GIN GALLERYやCRAFT MUSEUMのような専門店では、厳選された国内外のクラフトジンが豊富に用意されており、有料で試飲できるサービスも提供されています。これにより、消費者は購入前に好みのジンを見つけることができ、多様なクラフトジンを試す機会が提供されています。また、量り売りを行う店舗もあり、少量から様々な銘柄を試したい消費者にとって魅力的です。エシカル・スピリッツ・オフィシャルストアのように、蒸留所に併設された店舗では、ガラス越しに蒸留所を覗きながら、香水瓶でジンの香りを試したり、スタッフからジンのストーリーやボタニカルの話を聞いたりするなど、リカーショップとは異なる体験型の購入が可能です。蒸留所見学や試飲ツアーは、クラフトジンの物語を深く理解し、その魅力を体感する上で非常に価値のある体験です。桜尾蒸留所や紅櫻蒸溜所など、多くの蒸留所が見学ツアーや試飲の機会を提供しています。例えば、紅櫻蒸溜所では、蒸留所見学に加えて、併設の紅櫻公園本館でもクラフトジンの試飲販売を行っています。五島つばき蒸溜所では、地域の歴史や風土を巡るショートツアーと蒸留所見学、原酒試飲を組み合わせたプランも提供されており、これは単なる製品購入に留まらない、より深い文化体験を提供しています。このような体験型消費は、作り手の情熱やこだわりを直接感じることができ、製品への理解と愛着を深めることに繋がります。
まとめ
主要な知見の統合
国産クラフトジン市場は、その明確な定義の不在がもたらす自由度、地域固有の豊かなボタニカルの活用、そして伝統的な酒造技術と革新的な蒸留技術の融合によって、急速な成長を遂げています。特に、ウイスキーブームが新規蒸留所参入の触媒となり、酒税法改正と先行するクラフト酒類ブームが市場形成の下地を築きました。大手企業の戦略的投資と、量より質を重視し、製品の背景にある物語や持続可能性に価値を見出す消費者の行動変化が、市場の拡大を強力に後押ししています。国際的な品評会での多数の受賞は、その品質が世界レベルであることを証明し、海外市場での需要を牽引しています。
今後の展望と戦略的提言
国産クラフトジン市場は今後も成長が見込まれますが、持続的な発展のためには以下の戦略的提言が考えられます。
-
体験価値のさらなる強化と多様化:
蒸留所見学やテイスティングイベントの提供は、製品の物語性を伝え、消費者との感情的な繋がりを深める上で極めて有効です。今後は、地域文化との連携を強化したツアー(例:五島つばき蒸溜所のように地域の歴史や風土を巡るツアー)や、ボタニカルの収穫体験、ジン製造ワークショップなど、よりインタラクティブで没入感のある体験を提供することで、観光資源としての価値も高めることができます。これにより、国内外からの訪問者を惹きつけ、ブランドロイヤルティを構築することが可能となります。
-
持続可能性への取り組みの深化と情報発信:
廃棄物削減、地元農家との連携、地域資源の有効活用など、SDGsに貢献する取り組みは、現代の消費者の共感を呼び、ブランドイメージを向上させます。越後薬草の「YASO」シリーズのような循環型製造の事例を参考に、各蒸留所が独自の持続可能な取り組みを深化させ、それを積極的に情報発信することで、環境意識の高い消費者層からの支持をさらに獲得できるでしょう。これは、製品の付加価値を高め、市場における差別化要因となります。
-
国際市場における戦略的ポジショニングの確立:
日本産クラフトジンは既に国際的に高い評価を得ていますが、さらなる輸出拡大のためには、ターゲット市場の特性に合わせた戦略が必要です。日本ならではのボタニカルや伝統技術に裏打ちされた「和の要素」を明確に打ち出しつつ、各国の飲用習慣やカクテル文化に合わせた提案を行うことが重要ですし、国際的な品評会への継続的な出品と受賞歴の活用はもちろんのこと、海外のバーテンダーやインフルエンサーとの連携、オンラインでの情報発信強化を通じて、日本のクラフトジンのユニークな魅力を世界に発信し続けるべきです。
-
大手企業と小規模蒸留所の協調:
大手企業の市場参入は、ジンの認知度向上と飲用機会の拡大に貢献しています。一方で、小規模蒸留所は多様な製品と深い物語性を提供しています。今後は、両者がそれぞれの強みを活かし、例えば共同でのプロモーション活動や、大手企業の流通網を活用した小規模ブランドの展開支援など、協調関係を築くことで、市場全体のさらなる活性化が期待されます。これにより、消費者はより幅広い選択肢を享受し、市場は健全な競争と成長を続けることができるでしょう。
これらの戦略を通じて、国産クラフトジンは、単なるアルコール飲料に留まらず、日本の豊かな自然、伝統文化、そして職人の情熱を世界に伝える「文化的なアイコン」としての地位を確立し、持続的な成長を遂げることが期待されます。

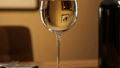
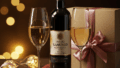
コメント